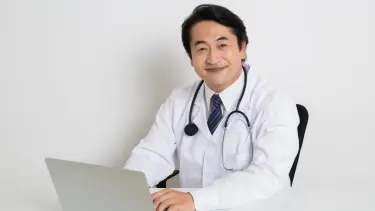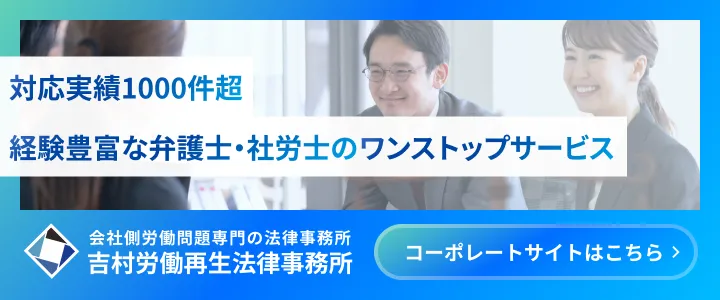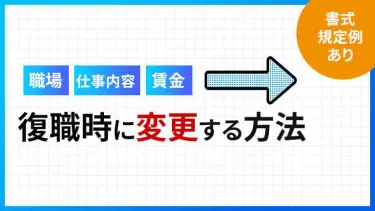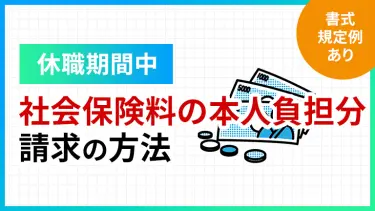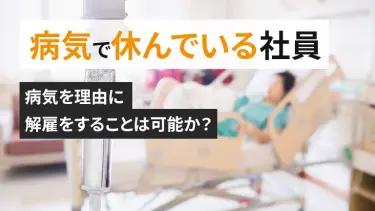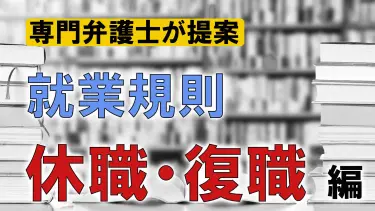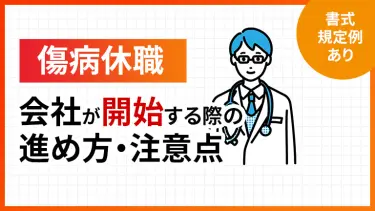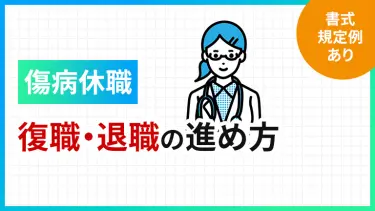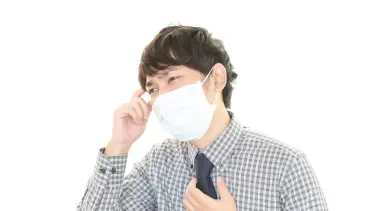就業規則に定めがなくとも,主治医の提出した診断書に合理的な疑問がある場合は,産業医への受診を命ずることができる。
復職の可否は会社が判断する
まず、押さえて頂きたいのは、復職可能性の判断権限は、安全配慮義務を負い人事権を持つ会社(使用者)にあるということです。
復職命令を出すというのは、それ自体が人事権の行使であり、使用者が専権で行使することです。
つまり、その権利を行使するのは、主治医でも産業医でもないのです。
もちろん、会社は,復職の可否の判断に際し,諸事情を考慮することが求められ、その際医師の診断が重要な資料となることはいうまでもありません。
実際にも、一般的な復職判断プロセスは,
② 主治医が,労働者が復職可能であるか否かを判断します。
③ 次に、産業医が,主治医の診断書や労働者との面談により当該労働者が復職可能であるか否かを判断します。
④ それらをふまえ会社が最終的に復職可能であるか否かの判断を行います。
という経過を辿ることが多いです。
ただ、実務では,傷病の治ゆないし復職の可否につき,労働者側が提出する主治医の所見と,会社側の指定医(産業医)の所見とが食い違うことがあります。
このような場合,会社としては、どのような点に留意し,復職の可否を判断すべきでしょうか。
主治医・産業医それぞれの診断書・意見書を確認・検討するに際してのポイントを説明します。
主治医の診断・意見
主治医とは
主治医とは「主となってその患者の治療に当たる医師。かかりつけの医師。」(広辞苑)のことです。
傷病休職の場面では、主治医は休職者が自分で選定し、継続的に診療を受け、復職に関する診断・意見を得ることが一般です。
主治医は、継続して休職者の病状を把握し治療していますので、求職者の健康状態を最も正確に把握しているという意味ではメリットがあります。
それゆえ,復職可否に関してもっとも的確な医学的判断ができるようにも思えます。
主治医のデメリット
しかし、主治医の復職に関する診断・意見については、次のようなデメリットがあります。
当該労働者の職務内容や職場環境の理解が欠けていること
主治医は休職者の健康状態については正確な診断は可能です。
もっとも、復職の可否を判断するためには、会社に存在する具体的な職務や職場環境の理解し、それらとの関係で問題なく就労することが出来るかの判断を行うことが不可欠です。
しかし、主治医は、本人の職務内容,職場環境,それらと発症の関係などの情報を十分に把握せずに復職可能との判断している場合があります。
それゆえ,主治医が労働者の復職が可能であると判断しても,当該労働者の労働契約の内容に即して就労可能である状態にまで回復しているとは必ずしも言い切れません。
厚生労働省が発した「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(平16.10.14策定、2020年7月改訂)においても「主治医による診断は、日常生活における病状の回復程度によって職場復帰の可能性を判断していることが多く、必ずしも職場で求められる業務遂行能力まで回復しているとの判断とは限りません。このため、主治医の判断と職場で必要とされる業務遂行能力の内容等について、産業医等が精査した上で採るべき対応を判断し、意見を述べることが重要です」と記載され、主治医の判断をそのまま採用することはできないことが指摘されています。
労働者の意向が反映されがち
また、主治医の復職可とする診断書には,休職者の「復職したい」という意向が反映されている可能性があり,医学的に正確ではない可能性があります。
主治医としては「患者がかわいそうなので、頼まれて書いた」「大企業なんだから、多少問題があってもひとまず復職させて面倒みてやってください」という発想なのかもしれません。
しかし、不十分な回復状態で復職を認めることは、当該休職者の健康管理上・安全配慮義務の履行という点で問題があるばかりか、他の従業員への負担という点でも問題があります。
会社としては、あくまでも医学的に正確な診断・意見のみを採用すれば足り、疑義の残る主治医の診断・意見は却下することも可能ですし、そうするべきです。
裁判例でも、主治医の作成した診断書は、労働者から「会社からクビを宣告されて,焦って目が覚めた」「会社に戻りたい,頑張ろうと思う」「制限勤務の診断書では就労可能ではないと判断されてしまうこともあるので,通常勤務は問題ないと書いてください」と頼まれて記載したものであるなどと認定し、その信用性を否定した裁判例があります(コンチネンタル・オートモーティブ事件 横浜地裁平27. 1.14決定 労経速2244号3頁)。
主治医との正しい関わり方
では,主治医には上記のようなメリット・デメリットがあるとして,どのように関わればよいでしょうか。
会社が主治医から意見聴取する
主治医が作成した診断書等だけでは十分な情報が得られないときは、産業医を通じて、あるいは人事担当者が、直接主治医と面談する必要があります。
主治医との面談のポイントは次のとおりです。
① 診察時間・期間・頻度の確認
② 診察の時期、経緯 の確認
③ 診断の際に前提とした資料(特に、休職者の業務内容や職場環境)の確認
④ 休職者の実際の職務内容を十分に説明する
⑤ ④を前提に通常程度に遂行できるまで回復したといえるのか
⑥ 復職に際しての条件の有無
⑦ 将来的に再発することなく継続的な労務提供が可能か
なお、面談の内容はメモや録音等により記録を取っておいてください。
J学園(うつ病・解雇)事件(東京地裁平22.3.24判決 労判1008号35頁)
傷病を理由とする解雇を争う事案において、裁判所は「被告は、原告の退職の当否等を検討するに当たり、主治医であるA医師から、治療経過や回復可能性等について意見を聴取していない。これには、F校医が連絡しても回答を得られなかったという事情が認められるが、そうだとしても……、被告の人事担当者であるM教頭らが、A医師に対し、一度も問い合わせ等をしなかったというのは、現代のメンタルヘルス対策の在り方として、不備なものといわざるを得ない」として主治医への確認を怠ったことが解雇が不相当であったことを裏付けるとして解雇を無効と判断しました。
マルヤタクシー事件(仙台地判昭61.10.17 労判486 号91 頁)
詳細な理由を付したうえで傷病労働者の疾病が治癒し後遺症もないこと,したがってタクシー運転も可能である旨の診断が明記されていた診断書が提出されていたにもかかわらず,当該労働者の復職を拒否したことが,復職拒否における労働者に対する合理的理由の明示という要件を欠き,違法,無効であると判断した
K社事件(東京地裁平17.2.18判決労判892号80頁)
J学園事件と同様の趣旨の判示を行っています。
主治医との面談に労働者が同意しない場合
主治医の意見聴取を行う場合、個人情報の第三者提供の問題やプライバシー保護の観点から、主治医は、情報提供に関する当該労働者本人の承諾を要求することが通常です。
実務においてもその同意をとってかかる意見聴取が進められています。
もし、説得を繰り返しても、産業医や会社の担当者が主治医と面談することを休職者が同意しない場合は、「主治医との面談が出来なければ、主治医の診断書の信用性を会社が判定できません。それゆえ、主治医の診断書を判断資料とは採用せずに会社は復職の可否を判断します。現状として他に治癒を証明する有効な証拠もありませんので、休職事由は消滅せず、よって、就業規則の規定により当然退職となる見込みです。」と文書で告知しておいたほうがよいでしょう。
これを受ければ、大抵の場合、復職したい休職者は産業医への面談に同意します。
労働者の同意を明確に義務づけるべく就業規則にもその旨明記しておいた方がよいでしょう。
面談費用について
主治医から意見聴取をする際には、費用が必要となるのが通常です。その場合は、会社の負担とする方がよいでしょう。
本来は治癒について証明責任を負うのは休職者ですが、主治医の診断書について会社の判断で確認を行うことになりますので、会社の負担と考えられます。
産業医の診断・意見
産業医との関わり方
産業医は、労働安全衛生法で、使用者が選任を義務付けられて選任した医師のことを言います。
先述のとおり主治医は、会社における休職者の職務内容や職場環境についての情報を得ていない場合も多く、また、休職者の意向に沿って診断書を作成する場合もあり、会社としてはチェックは不可欠です。
しかし、会社は医学についての専門性がないことが通常ですので、場合によっては、専門家の助言や意見を得る必要があります。
そこで、休職者者の職務内容や職場環境を知る産業医が,主治医の判断を精査し,あわせて復帰後に予定される職務内容や職場環境を考慮して,復職可能であるか否か,場合によっては,どのようにすれば復職が可能であるかを,判断してもらいます。
厚生労働省が発した「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(平16.10.14策定、2020年7月改訂)においても「主治医による診断は、日常生活における病状の回復程度によって職場復帰の可能性を判断していることが多く、必ずしも職場で求められる業務遂行能力まで回復しているとの判断とは限りません。このため、主治医の判断と職場で必要とされる業務遂行能力の内容等について、産業医等が精査した上で採るべき対応を判断し、意見を述べることが重要です」と記載され、産業医の重要性が明記されています。
産業医と休職者の面談
休職者から提出された主治医の診断書や意見書に疑義がある場合は、産業医その他会社が指定する医師の診断ないし面談を受けるよう命じ、その結果を踏まえた産業医あるいは指定医の意見を収集することになります。
産業医・指定医と休職者の面談・診察は、就業規則に根拠条項があればそれに基づいて行います。
根拠条項がない場合であっても、労使間の信義則ないし公平の観念に照らし、合理的かつ相当な理由のある場合は、休職者に対し、使用者が指定する医師の診断を受けるよう命ずることができます(電電公社帯広局事件最高裁一小昭61. 3.13判決労判470号6頁、T&Dリース事件大阪地裁平21. 2.26判決労経速2034号14頁、京セラ事件東京高裁昭61.11.13判決判時1216号137頁)。
なお、産業医との面談させて意見を聴取することが必要かつ容易な場合において、それを怠った場合は、復職拒否が無効と判断されることがありますので注意が必要です。
裁判例でも、休職者が提出した医師の意見書の内容に疑問を呈しつつも、会社の産業医との面談の機会を用意せず、産業医からの意見聴取も実施しない中でなされた復職拒否の判断が「客観性を欠くというべきである」とされ、休職期間満了による退職の効力は生じない旨判示された事例があります(第一興商(本訴)事件東京地裁平24.12.25判決労判1068号5頁)。
産業医の意見の信用性
主治医の診断・意見の問題点は上記のとおりですが、それでは産業医の判断は手放しに信用出来るかといえば、そうではありません。
まず、産業医は主治医と異なり継続的に休職者の休職期間中の健康状態やその推移については直接把握していないことが通常です。
また、とくに嘱託産業医の場合には,活動が活発でなかったり,当該企業の就労環境や職務内容を十分熟知しえなかったりする場合もあります。
また嘱託産業医が事実上自由に契約を解除されうる立場にあることから判断の独立性・中立性が脅かされるおそれもないとはいえません。雇われている身分の弱さから、会社の意向に沿った診断・意見を行う場合もありえるということです。
さらに、産業医が当該休職者の傷病に関する医学的専門性に欠ける場合もあります。メンタルヘルス不調の休職者に対して、内科専門医が診断・意見を述べた場合にどこまで信用出来るのかが問われます。
そこで、産業医・指定医の診断・意見についても、その信用性については、①主治医からの情報提供を得るなどして労働者の心身状況を適切に把握していたか、主治医との間で相互に情報交換して労働者の心身状況に係る共通認識を得ていたか、②休職者の職務内容や就労環境を適切に把握していたか、③医師の属性(嘱託産業医、指定医、専門分野・経歴)などを総合考慮して判断することになります。
産業医の診断より主治医の診断が優先された裁判例
東京都葬祭業協同組合事件 東京地裁R6.9.25判決 労経速2575号3頁
復職可否の判断において、就業規則で定められた産業医の診断ではなく、主治医の診断と診療経過を重視した裁判所が、自然退職の効力を否定し、労働契約上の地位を認めた事案。
【事案】
原告は、適応障害により休職していたが、主治医から「12月1日から復職可能」との診断を受けて復職届を提出。しかし被告は、就業規則に基づき指定医とした産業医の「就労困難」との診断に基づき休職を延長し、最終的に「休職期間満了による自然退職」とした。原告はこれを不当として、労働契約上の地位確認と賃金支払等を求めた。
【結論】
原告の請求を一部認容。裁判所は、令和3年12月1日時点で適応障害は職務遂行可能な程度にまで回復しており、休職事由は消滅していたと認定。自然退職の効力を否定し、原告の地位を認めた。
【理由】
・主治医は11月24日に「復職可能」、12月22日には「寛解」と診断し、翌年3月には終診とされていた。
・診療録には、8月以降症状の改善が見られ、10月以降は具体的症状の訴えもなくなっていた。
・裁判所は「従前の職務を通常の程度に行える程度にまで回復していれば休職事由は消滅する」と判断し、通院や服薬の継続は復職不能の決定的要素ではないと述べた。
・産業医の診断は、「一時的な回復の可能性」への抽象的懸念を指摘するにとどまり、症状の経過や主訴の聴取も不十分であり、主治医の診断を否定する根拠としては不十分と評価された。
・原告は復職届を提出しており、就労意思も明確と認定された。
【ポイント】
・復職判断では、継続的な治療経過と主治医の具体的診断が重視された
・就業規則に基づく産業医の診断よりも、診断根拠の具体性・合理性が優先された
・症状が完全に消失していなくても、通常の職務遂行が可能な程度の回復であれば復職は認められる
・主治医と産業医の診断が分かれた場合、診療の継続性と内容の具体性が決定的となる
【主治医の診断内容と裁判所の評価】
・原告は、令和3年4月から適応障害で通院していたが、令和3年11月24日の診察で、主治医は「抑うつ、不眠、全身倦怠感が改善し、12月1日から復職可能」と診断。
・その後の12月22日には「寛解」と診断し、令和4年3月2日に終診とされた。
・診療録には、8月以降に「笑うことができるようになっている」等の改善が見られ、10月以降は症状訴えが記載されていなかった。
・裁判所は、12月1日時点で「従前の職務を通常の程度に行える程度にまで回復していた」と認定。
・「症状が完全に消失し、通院や服薬が不要になることまでは必要ない」とし、主治医の判断を信頼すべき医学的評価とした。
【産業医(指定医)の診断内容と裁判所の評価】
・産業医は12月6日の診察で「一時的な回復の可能性があるが、このまま仕事を続けるのは難しい」とし、1か月の環境調整・加療・服薬指導を要する旨を診断。
・この際、原告は「夜は眠れる」「気分の落ち込みはない」「1か月間、薬を飲んでいない」等と述べたが、診療レポートには症状の経過について詳細な記載はなかった。
・裁判所は、産業医の診断を「抽象的な懸念の指摘にとどまり、症状の経過に基づく十分な評価とはいえない」と判断。
・そのため、「指定医の診断書のみで休職事由の継続を認定し、復職を拒否するのは相当ではない」と結論づけた。
【総合評価】
・復職可否の判断について、裁判所は診断の具体性・継続的な診療実績を重視。
・主治医の復職可診断を正面から採用し、産業医の診断はその裏付けの乏しさから限定的評価にとどめた。
・就業規則に基づき指定医を復職判断の基準とするという会社側の主張は、「自然退職の効力に直結する重要事項」として、就業規則の定めのみで専断的に決することはできないと否定された。
【認定された規定内容】
・被告の就業規則(36条~38条)には、休職及び復職に関する規定が設けられていた。
・具体的には、復職にあたっては、被告が指定した医療機関での受診結果に基づいて、就労の可否を判断する運用がなされていた。
被告はこの規定を根拠に、原告が提出した主治医の「復職可能」の診断書を受け入れず、指定医(産業医)の「就労困難」という診断を重視して復職を拒否し、休職期間満了による自然退職とした。
【就業規則に関する裁判所の評価】
・裁判所は、「就業規則の内容にかかわらず、主治医の診断書等の資料が提出されている場合には、指定医の診断結果のみで休職事由の消滅を否定することは許されない」と明言した。
・復職可否の判断が労働契約終了(自然退職)の効力に直結する以上、形式的に就業規則の文言を機械的に適用することは妥当でないとされた。
したがって、復職判断の運用実務においては、就業規則の形式だけでなく、個別の診断内容・治療経過等を実質的に評価する必要があることが示されました。
まとめ
主治医であれ、産業医であれ、会社が復職の可否を判断するに際して重要な医学的見地に基づく情報源であることは間違いありません。
それぞれ、休職者との関わり方、休職者の健康情報へのアクセスの度合、会社における職務内容や就業環境に関する情報量、会社との関わり方などが異なりますので、それぞれの特性に留意しつつ活用することが会社には求められます。
よって、主治医か産業医か、という二者択一の考え方は全くナンセンスです。どちらの医師の見解も適切に取り入れることが重要なのです。
最初に触れたとおり最終的に判断するのは人事権を持つ会社です。
医師の専門的知見を活用しながら、判断を適正に行い、不要なトラブルを回避することが重要です。