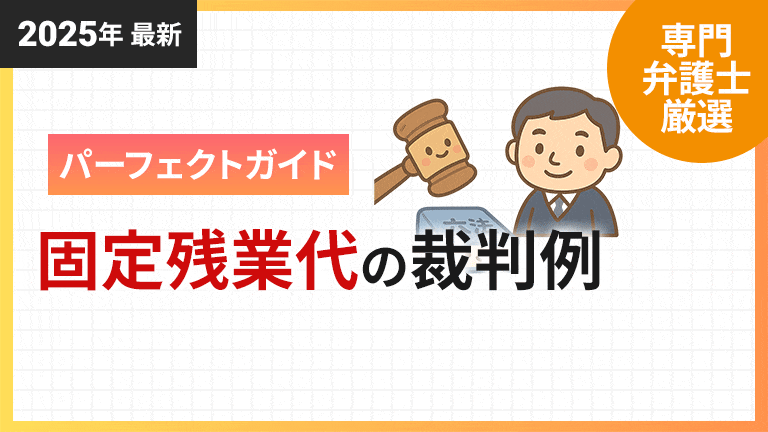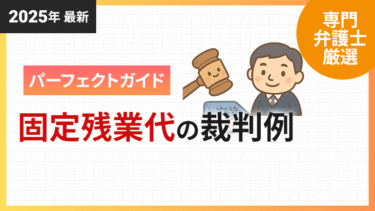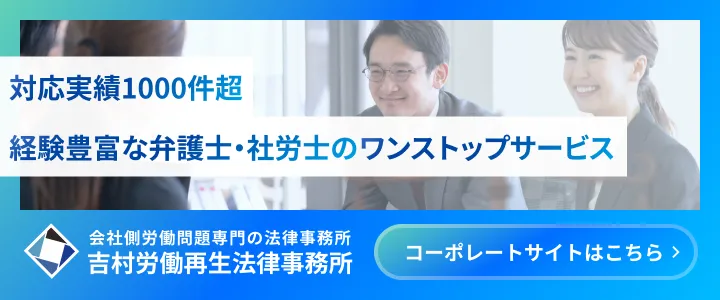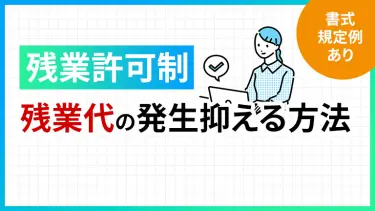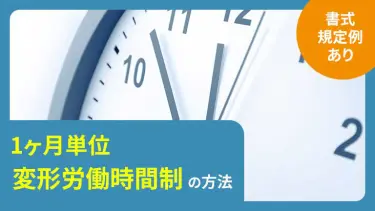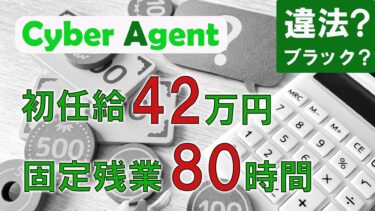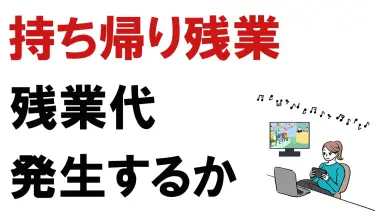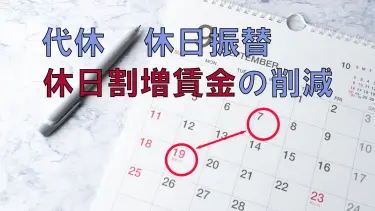固定残業代制度の有効性をめぐっては、これまで数多くの裁判例が積み重ねられてきました。これらの司法判断は、時代ごとの解釈の変遷を映し出し、企業実務に大きな影響を与えています。
本記事では、固定残業代に関する重要な裁判例を専門弁護士が厳選し、その判断のポイントを時系列に沿ってご紹介します。
これにより、固定残業代に関する司法判断の大きな流れを掴んでいただき、貴社の労務管理体制を見直す一助となれば幸いです。
なお、固定残業代の基本的な仕組みや有効要件、具体的な就業規則・雇用契約書の規定例については、以下の関連記事をご参照ください。
第1章 固定残業代 判断の萌芽とリーディングケースの確立(~平成6年)
固定残業代制度の有効性が司法の場で本格的に議論されるようになったのは比較的近年のことですが、その判断基準の礎となる考え方は、平成初期の裁判例において徐々に形成されていきました。
この章では、特に固定残業代に関する議論の方向性を決定づけた初期の重要な最高裁判決を、解説します。
小里機材事件(最一小判昭63.7.14労判523号6頁)【組込型・無効】★★☆
1.本判決の意義
高知県観光事件(後述)より古い最高裁判決ですが、固定残業代の有効要件について直接判断したものではなく、その点に関する言及は第一審判決の「傍論」(判決の結論に直接関係ない部分での意見)に過ぎません。
この一審傍論が、後の「明確区分性」「差額支払合意」などの議論のきっかけの一つとなったものの、本判決自体を最高裁が固定残業代の有効要件を示したリーディングケースと解釈することは誤りであると考えられます。
2.事案
(1) 事案の概要
工業用皮革等の加工販売業を営むY社において、時間外割増賃金の算定基礎から住宅手当、皆勤手当、乗車手当、役付手当が除外されていました。
これに対し、従業員である原告らが、これらの手当を算入して計算した割増賃金と既払分との差額、およびそれと同額の付加金の支払いを求めた事案です。
基本的には、除外賃金該当性が争点でした。
(2) 当事者の主張
従業員側:時間外労働に対する割増賃金の計算の基礎とすべき賃金は、基本給及び住宅、皆勤、乗車、役付の各手当である
会社側:① 基礎賃金は基本給のみである ② 抗弁として、定額残業代の合意があった → この結果、定額残業代の合意についても争点となりました。
(3) 定額残業代に関する規程・契約内容
原告の一人であるX1 ・Y間で、月15時間の時間外労働に対する割増賃金を本来の基本給に加算してX1の基本給とする旨の合意があった、すなわち月15時間の時間外労働を見込んだ上で、本来の基本給15万円、割増賃金1万5,600円の合算額である16万5,600円をX1の基本給とした。) と主張しました
しかし、就業規則や個別の雇用契約書には、固定残業代に関する明確な定めはありませんでした。
(4) 結論
第一審、控訴審、最高裁いずれも、従業員側の請求を認め、会社側の主張(固定残業代合意の存在)を退けました。
(5) 争点に関する判旨(定額残業代合意について)
第一審は、会社が主張する「月15時間分の割増賃金を基本給に含める合意」について、①15時間という数字の根拠が不明確、②会社が実際の残業時間を調査していない、③超過分の差額支払いの説明がない、といった理由から、そのような合意があったとは認められないと判断しました。
その上で、【傍論として】「仮に、月15時間の時間外労働に対する割増賃金を基本給に含める合意がされたとしても、①その基本給のうち割増賃金に当たる部分が明確に区別されて合意がされ、かつ、②労基法所定の計算方法による額がその額を上回るときはその差額を当該賃金の支払期に支払うことが合意されている場合にのみ、その予定割増賃金額を当該月の割増賃金の一部または全部とすることができるものと解すべき」との見解を示しました。
東京高裁および最高裁はこの傍論部分については特に触れておりません。
3.分析・評価
判例としての位置づけ
小里機材事件は、定額残業代の有効要件を示した判例として広く知られていますが、実際には一審判決が傍論で言及したに過ぎません。
本件では定額残業代の合意自体が存在しないと認定されているため、有効要件の検討は本来不要でした。一審は「仮に合意があったとしても」という仮定で判断したものです。
この定額残業代の要件に関する記述は、結論を導く上で不要な部分でした。高裁・最高裁が支持したのは判決の結論部分であり、最高裁が上記判示内容を直接承認したわけではありません。
後のモルガン・スタンレー・ジャパン事件(東京地判平17.10.19・労判905号5頁)でも、「小里機材事件の裁判における本件合意の効力についての判示は傍論というべきである」と明確に指摘されています。
定額残業代の有効要件とその評価
一審判決の傍論に過ぎないものの、念のため、本判決が示した定額残業代の有効要件について検討します。
本判決が傍論で示した要件は以下の3点です:
- 明確区分性:定額残業代部分と通常の賃金が明確に区別できること
- 対価要件:一定額が定額残業代の趣旨で支給されていること
- 差額支払合意:労基法所定額に不足する場合に差額を精算する合意があること
対価要件の必要性について
対価要件が必要という判断は妥当です。従来の裁判例でも「定額残業代の趣旨で支給されたか」を検討する例が多く見られます(①朝日急配事件・名古屋地判昭58.3.25.労判411号76頁②関西ソニー販売事件・大阪地判昭63.10.26・労判530号40頁、③名鉄運輸事件・名古屋地判平3.9.6・判タ777号138頁など)。
就業規則や給与明細で「基本給30万円のうち6万円は月20時間の時間外労働の割増賃金分」などと明確に規定されていれば、この要件は満たされます。
しかし、本件のように明確な規定がない場合は、支払いの実質的な趣旨を判断する必要があります。
本件では、会社の事前説明や業務実態調査の有無を考慮して「合意がない」と判断されました。
明確区分性の必要性について
本件を端緒として、高知県観光事件判決以降、この要件の必要性が確立しました。
明確区分が求められる理由は、労働者が「支払われた定額残業代が法定の割増賃金額を下回っていないか」を計算できるようにするためです。
「金額」の明示は不可欠ですが、「時間」の明示までは必ずしも必要ないと考えられます。
定額残業代の金額が特定されていれば、法定額との比較計算が可能だからです。
差額支払合意の必要性について
本判決は「不足分があれば支払う旨の合意が必要」としています。
しかし、定額残業代を超える労働が発生した場合に割増賃金を支払うべきことは労基法上当然の義務であり、あえて差額支払合意を要件とする必要性はないと考えられます。
この点は多くの学説から批判を受けています。
4 実務上の対応策
本判決(第一審)は定額残業代の有効要件として明確区分性、対価要件、差額支払合意の3点を挙げていますが、これは地裁判決の傍論に過ぎません。
特に差額支払合意を要件とした点には問題があるため、実務上は明確区分性と対価要件を満たしていれば十分と考えられます。
ただし、上記の要件を確実に満たすためには、就業規則に明確な根拠規定を設けるべきです。
また、テックジャパン事件の最高裁判決(櫻井補足意見)の影響で差額支払合意を有効要件とする下級審判例も見られることから、実務上は差額支払合意についても明記しておくことが安全策といえるでしょう。
高知県観光事件(最二小判平6.6.13労判653号12頁)【組込型・無効】★★★
1.本判決の意義
本判決は定額残業代の有効要件について最高裁が初めて自らの判断を示したリーディングケースです。
高知県観光事件は、定額残業代の有効性に関して「明確区分性」および「対価要件」の必要性を明確に判示しました。
下級審裁判に対する拘束力を有する重要判例であり、後のテックジャパン最高裁判決(最一小判平24.3.8)でも引用されています。
特に本件は【組込型】の事案で、中でも【歩合給における基本給組込型】という特徴があります。
また、判決が「歩合給の額が時間外および深夜労働を行った場合においても増加せず」としている点の位置づけについても注意が必要です。
2.事案
(1) 事案の概要
原告Xらは高知県観光(Y社)に雇用されたタクシー運転手でした。
Xらの賃金は月間水揚高に一定率の歩合(勤務歴に応じて42%~46%)を乗じた金額で支払われていました。
Xらが時間外労働や深夜労働を行った場合でも、別途割増賃金は支給されていませんでした。
また、歩合給の中で「通常の労働時間の賃金部分」と「時間外・深夜の割増賃金部分」を区別することもできない状態でした。
このため、歩合給の中に割増賃金が含まれているかどうかが争点となりました。
(2) 当事者の主張
従業員側(X)の主張
昭和60年6月1日から62年2月28日までの期間について、時間外・深夜の割増賃金が支払われていないとして、午前2時以降の時間外労働および午後10時~翌日午前5時までの深夜労働に対する、労働基準法37条の割増賃金および同114条の付加金の支払いを請求しました。
会社側(Y)の主張
歩合給には時間外および深夜の割増賃金部分も含まれているから、請求にかかる割増賃金は既に支払い済みであると主張しました。
会社はその根拠として以下の3点を挙げました:
① Xらの入社時に、労務担当者が歩合給に各種割増賃金が含まれている旨を説明し、Xらがこれを承諾した
② Xら以外の他の乗務員も了承している
③ 他のタクシー会社における割増賃金を含んだ賃率と比較しても、本件歩合給の賃率に遜色はない
ただし、会社は歩合給に割増賃金が含まれているものの、基礎給の額を正確には確定できず、それに基づく割増賃金も正確には計算できないことは認めていました。
(3) 定額残業代に関する規程・契約内容
定額残業代に関する明文規程はなく、就業規則や個別契約にも定額残業代に関する定めはありませんでした。
会社は単に「歩合給には時間外および深夜の割増賃金部分も含まれている」と主張していました。
(4) 争点に関する判旨
最高裁は以下のように判示しました:
「Xらの請求については、本件請求期間にXに支給された歩合給の額が、Xらが時間外及び深夜の労働を行った場合においても増額されるものではなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもできないものであったことからして、この歩合給の支給によって、Xらに対して法37条の規定する時間外及び深夜の割増賃金が支払われたとすることは困難なものというべきであり、Yは、Xらに対し、本件請求期間におけるXらの時間外及び深夜の労働について、法37条及び労働基準法施行規則19条1項6号の規定に従って計算した額の割増賃金を支払う義務があることになる」
(5) 結論
会社には従業員に対する割増賃金支払義務があるとして、請求額全額が認容されました。
3.分析・評価
本判決の意義と背景
本判決は、歩合給制度における定額残業代の有効性について、最高裁が初めて明確な判断を示した重要判例です。
歩合給に割増賃金を組み込んで支払うことが残業代の支払い方法として認められるかという点について、判断基準を示しました。
労働基準法上、歩合給や出来高払いにも割増賃金規定(労基法37条)が適用され、「通常の労働時間の賃金」の計算方法も明確に定められています(労基則19条1項6号)。
過去にも歩合給に割増賃金を含めて支給する特約の有効性が争われた事例(合同タクシー事件・福岡地裁小倉支部判昭42.3.24.労民集18巻2号210頁、高橋商連事件・東京地判平5.3.23労判634号69頁)がありましたが、本判決はその判断基準を明確にしました。
固定残業代の有効要件についての分析
判決が示した有効要件
最高裁は次の表現で有効要件を示しました:
「歩合給の額が時間外および深夜労働を行った場合においても増加せず(①)、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもできない(②)ものであったことからして…割増賃金が支払われたとすることは困難」
この中で特に重要なのは以下の2点です:
1. 明確区分性(②):通常の労働時間の賃金部分と割増賃金部分とを判別できるかどうかという基準を歩合給にも適用しています。
2. 対価要件:明示的には触れられていませんが、従来の裁判例では「定額残業代の趣旨で支給されたかどうか」が検討されており、本判決も前提としていると考えられます。
「増額しない」という要素の位置づけ
判決が「時間外・深夜労働を行っても増額しない」点に触れていることについては、一見別個の要件のようにも見えますが、実際には明確区分性の判断材料(間接事実)と考えるべきです。
理由は以下の通りです:
– 賃金が残業分増額していれば、残業時間と残業代が確定でき、結果として基本給と残業代が判別可能になる
– 増額していなくても、判別さえできれば時間外手当が正しく支払われているか計算可能
– つまり「判別できるか」が本質的要件であり、増額は判別するための補助的指標に過ぎない
したがって判決の要件は「増額かつ判別」とではなく「増額ないし判別」と理解すべきです。
浜村彰教授も浜村彰「平成6年腱重要判例解説」ジュリスト臨時増刊1068号199頁において「時間外・深夜労働を行っても歩合給の額が増額しないときに割増賃金の不払いが推定されるという意味での補足的指標」と解釈しています。
歩合給における定額残業代制度の可能性
歩合給でも定額残業代制度の導入は可能です。
歩合給は本来、割合(%)で定められているため、時間外労働の実績も割合で反映させることができます。
残業時間の実態調査をして、想定される時間外労働時間が全労働時間の何%かを計算し、それに基づいて設定すれば、通常労働時間と時間外労働時間の区分けが可能になります。
本件でも会社は「42%の歩合のうち39%が通常の労働時間の賃金部分」と主張しましたが、同時に「基礎給の額を正確に確定できない」ことを認めていたため、判別可能とは認められませんでした。
仮に39%部分が確定的に基礎給と明確に定められていれば、区分が可能となり、通常の労働時間の賃金を計算した上で割増賃金額を算出できるため、歩合給の一部に割増賃金部分を含めることも不可能ではなかったでしょう。
ただし、その場合でも実際の時間外労働に応じて、設定した割増分(例えば3%)が法定の割増賃金額に足りないケースは生じ得るため、不足分は別途支払う必要があります。
※野間賢「労働判例百選〔第7版〕」参照
4.実務上の対応策
高知県観光事件の判断を踏まえると、実務上は以下の点に留意すべきです:
1. 有効要件の確保:定額残業代の有効要件として「明確区分性」と「対価要件」を確実に満たす設計にする。テックジャパン事件の最高裁判決も同様の要件を引用していることから、最高裁はこの2つの要件で十分との立場である。
2. 就業規則への明記:定額残業代制度を就業規則に明確に規定する。本件では規程がなかったが、有効要件を満たすためにも明文化は不可欠。
3. 歩合給での対応方法:
– 残業時間の実態調査を行い、想定される時間外労働時間が全労働時間の何%かを計算
– 基本給部分と時間外手当部分の割合を明確に定める(例:基本給〇%、時間外手当〇%)
– 計算結果を給与明細等に明示して、労働者が確認できるようにする
– 実際の時間外労働時間に応じて、設定額が不足する場合は差額を支払う仕組みを確立
このように適切に制度設計することで、歩合給においても有効な定額残業代制度を導入することは可能です。
ただし、基本的な要件を満たし、実際の運用においても労働者の権利が確保されるよう十分注意する必要があります。
第2章:高知県観光判決以降の展開と解釈の深化(平成7年~平成23年)
高知県観光事件最高裁判決(平成6年)は、固定残業代の有効性判断における「明確区分性」と「対価要件」という基本的な法的枠組みを打ち立てました。
この重要な判決を受けて、その後の下級審では、これらの要件が具体的にどのように解釈され、様々な事案に適用されていくのか、判断の積み重ねが見られました。
特にこの時期(平成7年~平成23年頃、次に紹介するテックジャパン事件最高裁判決が登場するまで)は、【手当型】の固定残業代の有効性や、「対価要件」の具体的な判断要素について、裁判所の解釈が深められていった時期と言えます。以下、この時期の代表的な裁判例を見ていきましょう。
SFコーポレーション事件(東京地判平21.3.27労経速2042号26頁)【手当型・有効】★☆☆
1.本事件を紹介する意義
本事件は、「管理手当」について、給与規定等に明記された文言に照らして時間外労働・深夜労働に対する割増賃金の内払いと認められた事案です。就業規則(賃金規程)の規定を検討する際に参考となる貴重な例といえます。
また、割増賃金額が定額残業代に満たない場合の差額を繰り越すことが認められた珍しい事例ですが、この判断には疑問点もあるため(4(3)参照)、実務上の留意が必要です。
2.事案
(1) 概要
不動産会社である被告Y社(SFコーポレーション)の従業員であった原告Xが、「管理手当」を割増賃金の算定基礎に含めるべきと主張して時間外労働・深夜労働に対する割増賃金の支払いを求めました。これに対してY社は、「管理手当」は時間外・深夜労働の割増賃金としての性質を持つため、算定基礎賃金には含まれないと反論し、争いとなりました。
(2) 「管理手当」に関する給与規定等の記載
ア.給与規定
「管理手当は、月単位の固定的な時間外手当の内払いとして、各人ごとに決定する」
「第16条に基づく計算金額と管理手当の間で差額が発生した場合、不足分についてはこれを支給し、超過分について会社はこれを次月以降に繰り越すことができるものとする」
※第16条の内容は判旨からは明らかではありませんが、時間外手当の算定方法等を定めた規定と考えられます。
イ 労働条件通知書兼同意書
「月単位の固定的な時間外手当の内払いとして、総合職8万円、一般職6万円を支給」
ウ.労働条件通知書兼同意書(更新用)
「管理手当(内払時間外手当) 月単位の固定的な時間外手当の内払いとして、月額8万円を支給。但し、今後当該従業員の時間外労働時間の実情に応じて金額が変更される場合がある。管理手当に含まれる時間外労働時間数の計算式は以下のとおり。
管理手当に含まれる時間外労働時間数=管理手当÷(【基本給十役職手当十特別手当十精勤手当】÷月平均労働時間×1.25)」
エ.給与支給明細書
「管理手当(残業内払)」
(3) 争点
Y社は、給与規定に基づき、「管理手当」は時間外労働・深夜労働に対する割増賃金の内払いとしての性質を持つため、割増賃金の算定基礎から除外されると主張しました。そのため、「管理手当」が時間外手当等に当たるか否かが主な争点となりました。
Xは、「管理手当」は外勤・内勤に関わらず一律支給されているなど、残業手当の性質を持たないと反論しました。
3.判決の内容
本判決は、労働条件通知書、給与規定、給与支給明細書の記載内容から、「管理手当」は時間外・深夜労働の割増賃金の内払いであると認められると判断し、Xの主張を採用しませんでした。
4.検討
(1)「明確区分性」と「対価要件」について
上記の給与規定等の記載によれば、「管理手当」は明確に区分されており(明確区分性)、また時間外労働の対価としての性格も明らかです(対価要件)。したがって、「管理手当」を時間外・深夜労働の割増賃金の内払いと認めた本判決の判断は妥当といえるでしょう。
なお、本判決がなぜ「管理手当」に時間外割増賃金と深夜割増賃金の両方が含まれると解釈したのか、その理由は明示されていません。推測するに、労働条件通知書に記載された計算式中の割増率「×1.25」が、時間外・深夜両方の割増率を合わせたものと解釈された可能性があります。
(2)「差額支払合意」について
給与規定には「不足分があれば支給する」旨が明記されていたため、「差額支払合意」の要件も充足していたと解されます(実際に差額の支払いが行われていたかは明らかではありません)。
ただし、この差額支払合意の記載が裁判所の判断を左右したかどうか、つまり裁判所がこの要件を必須と考えていたかどうかは判決文からは明らかではありません。
(3) 超過分(管理手当−割増賃金)の繰越しに関する判断について
本判決は、管理手当が実際の割増賃金額を超過した場合に、その超過分を次月以降に繰り越せるとする給与規定の定めを有効とした点が特徴的です。
しかし、この判断には重大な問題があります。過払分の繰越しは、過去の賃金の過払分を将来の賃金から控除することになるため、将来の賃金を減額して支払うことになり、賃金全額払いの原則(労基法24条1項)との関係で問題となります。
最高裁はこの点について、過払いからの時間的接着性や控除金額の多寡などに着目して判断しています。
具体的には:
1. 過払いから2~3か月以内の控除であれば賃金全額払いの原則に反しないとした事例(福島県教組事件・最判昭44.12.18)
2. 過払いから3~5か月後の控除については、賃金全額払いの原則に反するとした事例(群馬県教組事件・最判昭45.10.30)
本件では、超過分の繰越期間について何の限定もなく、かつ繰越金額が多額に及ぶ可能性があることから、本判決の判断には疑問が残ります。
さらに、このような繰越制度を認めると、定額残業代制度の主なメリットである給与計算の簡素化や長時間労働の抑制効果が失われることになります。また、使用者が残業代を支払わないための方便として定額残業代制度を利用しているという疑念を招き、制度自体の有効性が否定されるリスクも生じます。
5.本判決を踏まえた実務対応
本判決からも明らかなように、定額残業代制度を導入する場合は、就業規則等において「割増賃金の対価である旨」を明記すべきです。
また、超過分(定額残業代−割増賃金)の繰越しについては、上記のとおり問題があるため、避けるべきでしょう。
会社側にとって一時的に有利に見えても、定額残業代制度自体の有効性が否定されるリスクがあります。
なお、定額残業代制度を導入する際には、その前提となる時間外労働の実態調査を行い、合理的な時間数・金額設定を行うことも重要です。
また、従業員への説明を丁寧に行い、制度の趣旨や内容について理解を得ることも必要でしょう。
ことぶき事件(最二小判平21.12.18労判1000号5頁)【手当型・有効】★★☆
1.本判決を紹介する意義
本判決は、一般に「管理監督者の深夜割増賃金請求」という論点で有名な最高裁判決ですが、定額残業代の有効性の観点からも極めて重要です。
特に、「労働協約、就業規則その他によって一定額の深夜割増賃金を含める趣旨で定められていることが明らか」であれば、深夜割増賃金を含める趣旨で賃金を支払うことが可能と明確に判示した点が注目されます。
最大の意義は、差額支払合意を定額残業代の要件として要求していない点です。
つまり、本判決は定額残業代の実務において重要な先例的価値を持つ最高裁判決として再評価されるべきものです。
2.事案
(1) 概要
上告人X(一審原告)は理髪店チェーンを経営する被上告人Y社(ことぶき)で総店長として勤務していました。Xは退社の際にY社の顧客カードを無断で持ち出し、転職先の理髪店で使用しました。
Y社がXに対して不正競争行為・不法行為に基づく損害賠償を請求したところ、Xは反訴として時間外給与等の支払いを求めました。
第1審・原審ともY社の損害賠償請求を一部認容し、Xの反訴請求を棄却しました。
特に原審は、Xが管理監督者に該当すると判断し、深夜割増賃金を含めた反訴請求全体を棄却したため、Xが上告しました。
(2) 定額残業代についての定め
本件では具体的な定額残業代に関する明示的な定めはありませんでした。
Xは所定の給与(平成16年3月までは月額43万4,000円、同年4月以降退社までは39万0,600円)に加え、店長手当として月額3万円が支給されていました。
第一審が認定した事実によれば、同16年3月頃までの賃金は他の店長の約1.5倍でした。
(3) 争点
ここでは管理監督者の深夜割増賃金に焦点を当てます。
特に、①管理監督者にも深夜割増賃金請求権があるか、②Xの所定賃金に深夜割増賃金が含まれていたかが主な争点でした。
3.判示内容(一部破棄差戻し)
(1) 管理監督者の深夜割増賃金について
「労基法41条2号の規定によって同法37条3項の適用が除外されることはなく、管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができるものと解するのが相当である。」
(2) 深夜割増賃金の支払について
「管理監督者に該当する労働者の所定賃金が労働協約、就業規則その他によって一定額の深夜割増賃金を含める趣旨で定められていることが明らかな場合には、その額の限度では当該労働者が深夜割増賃金の支払を受けることを認める必要はないところ、原審確定事実によれば、上告人の給与は平成16年3月までは月額43万4,000円、同年4月以降退社までは月額39万0,600円であって、別途店長手当として月額3万円を支給されており、同16年3月ころまでの賃金は他の店長の1.5倍程度あったというのである。したがって、上告人に対して支払われていたこれらの賃金の趣旨や労基法37条3項所定の方法により計算された深夜割増賃金の額について審理することなく、上告人の深夜割増賃金請求権の有無について判断することはできないというべきである。」
4.本判決の検討
判例としての位置づけと差額支払合意の不要性
本判決は、理髪店チェーンの総店長という管理監督者にも深夜割増賃金請求権があると明確に認めた点で重要です。
さらに定額残業代の観点から見ると、「所定賃金が労働協約、就業規則その他によって一定額の深夜割増賃金を含める趣旨で定められていることが明らか」であれば、差額支払合意がなくとも定額残業代としての効力を認めるとした点が極めて重要です。
具体的には:
1. 深夜割増賃金を所定賃金に含める場合の要件として、「趣旨が明らか」であること以外の要件は示されていない
2. 差額支払合意の必要性は一切言及されていない
3. 行政解釈(昭和63年3月14日基発150号、平成11年3月31日基発168号)を踏まえた判断と考えられる
本判決は深夜割増賃金に関するものですが、定額残業代に関する判断枠組みとして広く応用できると考えられます。
つまり、就業規則等で明記して割増賃金を含める趣旨が明らかであれば、差額支払合意がなくとも定額残業代としての弁済効果が認められるという原則を示したものと解されます。
深夜割増賃金の特殊性に関する留意点
なお、本判決は深夜割増賃金に関するものであることから、解釈の際には以下の点に留意する必要があります:
深夜割増賃金については、業務の性質上、深夜労働が前提となっている場合には「明確区分性」が緩やかに認められる傾向があります。これは下級審の複数の裁判例でも示されています:
– 大虎運輸事件(大阪地判平18.6.15労判924号72頁):完全歩合制のトラック運転手について、時間外・休日については判別困難としながらも、深夜業務が当然の前提とされていた実態を踏まえて深夜割増賃金の明確区分性を緩やかに認めた
– クアトロ事件(東京地判平17.11.11労判908号37頁)、千代田ビル管財事件(東京地判平18.7.26労判923号25頁)、藤ビルメンテナンス事件(東京地判平20.3.21労判967号35頁)なども同様の傾向
このような深夜割増賃金の特殊性は理解しつつも、本判決が示した「差額支払合意を要件としない」という判断枠組みは、定額残業代全般に適用可能な重要な法理であると考えられます。
5.本判決を踏まえた実務対応
本判決の判示内容を踏まえると、テックジャパン事件最高裁判決の櫻井補足意見が示した差額支払合意について、最高裁は必ずしも定額残業代の必須要件とは位置付けていないと考えられます。
したがって、訴訟等で差額支払合意が争点となった場合、本判決を引用して反論することは有効な法的戦略となるでしょう。
特に、「所定賃金に割増賃金が含まれる趣旨が明らか」であることを立証できれば、差額支払合意がなくとも定額残業代としての効力が認められる可能性が高いといえます。
ただし、実務上のリスク管理としては、可能な限り差額支払合意を設けておくことが望ましいことに変わりはありません。
特に新規に定額残業代制度を導入する場合は、「割増賃金を含める趣旨」を明確にするとともに、差額支払条項も設けるという対応が安全です。
東和システム事件(東京高判平21.12.25労判998号5頁)【手当型・有効】★★☆
1.本判決を紹介する意義
本事件は、管理監督者に支給されていた「特励手当」が定額残業代として認められた事例として重要です。特に注目すべきは、給与規程等に明文で「割増賃金の対価である」旨の記載がなかったにもかかわらず、給与規程上の位置づけや諸般の事情を総合的に考慮して、この手当が時間外労働等の対価であると認められた点です。
このことは、管理監督者等の残業代支払対象外とされている従業員に支給される手当であっても、明文規定がなくとも実質的な判断によって定額残業代として認められる可能性を示しており、実務上参考になる事例といえます。
2.事案
(1) 概要及び争点
一審被告・控訴人Y社(東和システム)において課長代理職として勤務していた一審原告・被控訴人Xら3名が、時間外労働に対する割増賃金の支払いを求めました。
Y社は、まず第一の主張として「Xらは管理監督者に当たるため残業代支払いの対象外」と主張しました。
第二の主張として、仮にXらに残業代請求権があるとしても、「特励手当」が時間外手当の性質を持つため、それによってすでに支払い済みであると反論しました。
裁判所は、Xらが管理監督者に当たらないと判断した上で、「特励手当」が時間外労働の対価(定額残業代)としての性質を持つかどうかを検討しました。
(2) 「特励手当」に関する給与規程の記載
「管理職務者(課長職及び同相当職以上のもの)及びこれに準ずる者(課長代理職)は、特励手当として基本給の30%を支給する。」
※注目すべきは、この規定が単に手当の支給を定めているだけで、時間外労働等の対価であるという明示的な記載がない点です。
3.本判決の内容
本判決は、以下の諸点を総合的に考慮し、「特励手当」が時間外労働(残業)の対価として支給されるものであると認定しました:
① 支給対象者の特性
「特励手当」は、所定時間外労働(残業)が恒常的に予定される職位(課長代理職以上)に支給されるものであること
② 算定方法の特徴
「特励手当」は基本給の30%に相当する金額であり、同じ課長代理職でも基本給が異なれば特励手当の額も異なること。
これは特励手当が職位だけでなく労働の対価としての性格を持つことを示唆
③ 給与体系における位置づけ
- 「特励手当」の前身である精励手当について、旧給与規程は「超過勤務手当は前条の精励手当受給者には支給しない」と明記し、両者が択一的関係にあることを示していた
- 実際の運用において、「特励手当」と超過勤務手当が重複して支給されたことはなかった
- 給与規程上、「特励手当」は超過勤務手当と同じく「基準外給与」として分類されていた
④ 給与額に関する事情
- 課長代理に昇進すると一般職時代の超過勤務手当に代わって「特励手当」が支給され、さらに課長に昇進すると「特励手当」のみとなる給与体系
- Xらの基本給(45~50万円)は低額に抑えられているとはいえない水準だったこと
4.検討
(1)「明確区分性」と「対価要件」について
「明確区分性」については、給与が「基本給」と「特励手当」として明確に区分されていたため、問題なく認められました。
一方、「対価要件」については、本件の特徴として給与規程等に手当が時間外労働の対価である旨の明記がなかった点があります。
しかし、裁判所は上記①~④の多角的な事情を総合考慮し、実質的に「対価要件」を満たすと判断しました。
この判断手法は注目に値します。すなわち、明文の規定がなくとも、実質的・総合的判断により定額残業代性を認める可能性を示しています。
ただし、本判決はその判断基準を明確に示しておらず、総合的な事例判断であるため、個々の事案の解釈や事実評価によって結論が変わりうることに留意すべきです。実際、第一審判決は「特励手当」を定額残業代と認めなかったという点からも、判断の難しさが伺えます。
(2)「差額支払の合意」について
本件では、給与規程等に差額支払についての定めがあったかどうかは明らかではありません。
Y社がXらを管理監督者として扱っていたことからすると、差額支払の合意はなかったと推測されます。
それにもかかわらず、本判決は「差額支払合意」を要件として求めていないと解され、この点は妥当な判断といえるでしょう。
差額支払義務は労働基準法上当然に発生するものであり、定額残業代の有効性を左右する独立の要件ではないという考え方が窺えます。
5.本判決を踏まえた実務対応
本判決は、明文規定がなくとも定額残業代として認められる可能性を示していますが、テックジャパン事件最高裁判決以降の裁判例の中には定額残業代の要件を厳格に解するものも多いことを考慮すると、新たに定額残業代制度を導入する際には、就業規則(賃金規程)において明確に「割増賃金の対価である旨」を明記するべきでしょう。
具体的には以下の点に留意すべきです:
1. 手当の名称を工夫し、時間外労働の対価であることが明確に分かるようにする
2. 就業規則や労働契約書に明記し、定額残業代の趣旨、金額、対象時間数を明確にする
3. 給与明細書にも区分して表示し、何時間分の時間外労働の対価かを明示する
4. 差額精算の仕組みを導入し、実際に超過分があれば支払う運用を確立する
5. 人事考課など時間外労働と関係のない要素で金額が変動する仕組みは避ける
これらの対応により、定額残業代の有効性が否定されるリスクを低減できるでしょう。
第3章:テックジャパン事件最高裁判決と新たな潮流の発生(平成24年~)
平成24年、固定残業代の有効性判断に関する議論に大きな一石を投じる最高裁判決が出されました。
それが「テックジャパン事件」です。この判決の法廷意見自体は、従来の判断枠組みを再確認するものでしたが、同時に出された櫻井龍子裁判官による「補足意見」が、その後の下級審の判断に強い影響を与え、固定残業代の有効性要件に関する議論を新たな段階へと進めることになりました。
この章では、まずこの画期的なテックジャパン事件最高裁判決の内容を詳しく見ていき、その後、この判決(特に補足意見)の影響が顕著に表れた下級審の裁判例を紹介していきます。
テックジャパン事件(最一小判平24.3.8労判1060号5頁)【組込型・無効】★★★
1.本判決を紹介する意義
本判決は、基本給に割増賃金が組み込まれているいわゆる【組込型】の定額残業代制度について、「通常の労働時間の賃金と割増賃金に当たる部分とを判別し得ることが必要」という要件(明確区分性)を充足していないとして、結論として定額残業代制度を無効とした最高裁判決です。
特に重要なのは、櫻井龍子裁判官による補足意見です。この補足意見では、明確区分性の要件をより厳格に解釈し、さらに「差額支払合意及びその実態」が定額残業代制度の有効要件であると明示的に述べています。この補足意見を受けて、その後の下級審判決で定額残業代制度の効力が否定されるケースが相次いでおり、実務上の影響が非常に大きい判決となっています。
2.事案
(1) 概要
人材派遣会社である被上告人Y社(テックジャパン)は、上告人Xを派遣労働者として雇用しました。
雇用契約では、基本給を月額41万円とした上で、以下の特殊な計算方法が定められていました:
– 1か月の労働時間が180時間を超えた場合:超過時間×2,560円を追加支給
– 1か月の労働時間が140時間に満たない場合:不足時間×2,920円を控除
Xは実際に法定時間外労働をしましたが、多くの月は180時間以下だったため追加支給はありませんでした。そこでXは、法定時間外労働に対する未払割増賃金等を請求しました。
第1審(横浜地判平20.4.24労判1060号17頁)は、基本給41万円のうち180時間までの時間外労働の基本部分は含まれているが割増部分(25%)は含まれていないとして、Xの請求を一部認容しました。原審(東京高判平21.3.25・労判1060号11頁)は、Xは時間外手当請求権を放棄したとして、180時間を超える分のみを認めました。これに対してXが上告したのが本件です。
(2) 定額残業代についての定め
雇用契約における定めは以下の通りでした:
– 基本給:月額41万円
– 月間総労働時間が180時間超の場合:超過時間×2,560円を追加支給
– 月間総労働時間が140時間未満の場合:不足時間×2,920円を控除
(3) 争点
- 月間180時間以内の労働時間中の時間外労働に対する割増賃金が基本給の中に含まれているか
- 月間180時間以内の労働時間中の時間外労働に対する割増賃金について、賃金放棄の意思表示があったか
3.判決の内容
(1) 明確区分性についての判断
「本件雇用契約は、(中略)基本給を月額41万円とした上で、月間総労働時間が180時間を超えた場合にはその超えた時間につき1時間当たり一定額を別途支払い、月間総労働時間が140時間に満たない場合にはその満たない時間につき1時間当たり一定額を減額する旨の約定を内容とするものであるところ、この約定によれば、月間180時間以内の労働時間中の時間外労働がされても、基本給自体の金額が増額されることはない。また、上記約定においては、月額41万円の全体が基本給とされており、その一部が他の部分と区別されて労働基準法37条1項の規定する時間外の割増賃金とされていたなどの事情はうかがわれない上、上記の割増賃金の対象となる1か月の時間外労働の時間は、1週間に40時間を超え又は1日に8時間を超えて労働した時間の合計であり、月間総労働時間が180時間以下となる場合を含め、月によって勤務すべき日数が異なること等により相当大きく変動し得るものである。そうすると、月額41万円の基本給について、通常の労働時間の賃金に当たる部分と同項の規定する時間外の割増賃金に当たる部分とを判別することはできないものというべきである。」
(2) 定額残業代制度の効力についての判断
「上告人が時間外労働をした場合に、月額41万円の基本給の支払を受けたとしても、その支払によって、月間180時間以内の労働時間中の時間外労働について労働基準法37条1項の規定する割増賃金が支払われたとすることはできないというべきであり、被上告人は、上告人に対し、月間180時間を超える労働時間中の時間外労働のみならず、月間180時間以内の労働時間中の時間外労働についても、月額41万円の基本給とは別に、同項の規定する割増賃金を支払う義務を負うものと解するのが相当である(最高裁平成3年(オ)第63号同6年6月13日第二小法廷判決・裁判集民事172号673頁参照)。」
(3) 櫻井龍子裁判官の補足意見
① 明確区分性の趣旨
「労働基準法37条は、同法が定める原則1日につき8時間、1週につき40時間の労働時間の最長限度を超えて労働者に労働をさせた場合に割増賃金を支払わなければならない使用者の義務を定めたものであり、使用者がこれに違反して割増賃金を支払わなかった場合には、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられるものである(同法119条1号)。このように、使用者が割増の残業手当を支払ったか否かは、罰則が適用されるか否かを判断する根拠となるものであるため、時間外労働の時間数及びそれに対して支払われた残業手当の額が明確に示されていることを法は要請しているといわなければならない。そのような法の規定を踏まえ、法廷意見が引用する最高裁平成6年6月13日判決は、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別し得ることが必要である旨を判示したものである。本件の場合、その判別ができないことは法廷意見で述べるとおりであり、月額41万円の基本給が支払われることにより時間外手当の額が支払われているとはいえないといわざるを得ない。」
② 定額残業代が認められる具体例
「便宜的に毎月の給与の中にあらかじめ一定時間(例えば10時間分)の残業手当が算入されているものとして給与が支払われている事例もみられるが、その場合は、その旨が雇用契約上も明確にされていなければならないと同時に支給時に支給対象の時間外労働の時間数と残業手当の額が労働者に明示されていなければならないであろう。さらには10時間を超えて残業が行われた場合には当然その所定の支給日に別途上乗せして残業手当を支給する旨もあらかじめ明らかにされていなければならないと解すべきと思われる。
本件の場合、そのようなあらかじめの合意も支給実態も認められない。」
4.本判決及び補足意見の検討
(1) 本判決の位置づけ
本判決は、組込型の定額残業代制度において「明確区分性」の要件を充足していないとして制度を無効とした判決です。
この判断自体は、これまでの判例(特に高知県観光事件最高裁判決)の考え方に沿うものです。
本判決が引用しているのは高知県観光事件最高裁判決であって小里機材事件ではない点にも注目すべきです。
つまり、本判決は、定額残業代制度の有効性判断において、高知県観光事件の判断枠組みを先例と位置づけていると考えられます。
また、本判決の射程はあくまで【組込型】の定額残業代制度の事案に限られる点も重要です。
つまり、本判決の判断枠組みをそのまま【手当型】の事案に適用することは適切ではありません。
(2) 補足意見の検討
① 補足意見の射程
櫻井補足意見は、本件と同様の【組込型】の事例を前提として論じている点に注意が必要です。
具体例として挙げているのも、「便宜的に毎月の給与の中にあらかじめ一定時間の残業手当が算入されているもの」という【組込型】の事例です。したがって、【手当型】の定額残業代制度には必ずしも妥当しないと考えられます。
また、補足意見はあくまで「一裁判官の個人的見解」であり、最高裁としての公式見解ではない点も重要です。
② 明確区分性の厳格解釈
補足意見は、明確区分性の要件について、「雇用契約上の明確化」だけでなく「支給時における時間外労働の時間数と残業手当額の明示」まで要求しています。しかし、明確区分性の本来の趣旨は「通常賃金部分と割増賃金部分を判別できるようにすること」であり、金額の明示で十分と考えられます。
時間数の明示まで必要とする論理的な根拠は示されておらず、法令解釈としては疑問が残ります。おそらく補足意見は、【組込型】の明確区分性を確保するための望ましい方法の一例として述べたものと理解すべきでしょう。
③ 差額支払合意の要件化
補足意見は、「定額残業時間を超えて残業が行われた場合は別途上乗せして残業手当を支給する旨のあらかじめの明示」を求めています。これは実質的に「差額支払合意」を定額残業代制度の有効要件とする考え方です。
しかし、差額支払義務は労基法上当然に発生するものであり、差額を支払わなかったとしても、その分の未払いが生じるだけで、定額残業代制度自体の有効性に影響すべきではないと考えられます。
また、差額支払合意を有効要件とする考え方は、ことぶき事件最高裁判決とも整合しない点に注意が必要です。同判決では、差額支払合意の有無に触れることなく、「一定額の割増賃金を含める趣旨が明らか」であれば足りるとしています。
5.本判決及び補足意見を踏まえた実務対応
本判決自体は【組込型】の明確区分性に関する従来の判例の考え方を確認したものですが、補足意見に示された考え方(特に差額支払合意の要件化)がその後の下級審判決に大きな影響を与えています。
このため、実務上は補足意見の影響を考慮した対応が必要です。
特に新たに定額残業代制度を導入する際には:
1. 【手当型】を採用する
– 基本給とは別に「時間外労働手当」等の名称で明確に区分する
2. 就業規則等で明確に規定する
– 手当の金額と対応する時間数を明示する
– 給与明細書等でも区分して表示する
3. 残業の実態に即した設計にする
– 対象者の実際の残業時間を調査し、適切な時間数・金額を設定する
– 職種や部署ごとに合理的な差を設ける場合はその根拠を明確にする
4. 差額支払条項を設ける
– 定額残業時間を超えた場合の差額支払いを明記する
– 実際に差額が生じた場合は確実に支払う
これらの対応により、定額残業代制度が無効とされるリスクを最小化できるでしょう。
アクティリンク第一事件(東京地判平24.6.29)【手当型・無効】★☆☆
1.本判決を紹介する意義
本判決は、定額残業代の有効性判断において「差額支払合意」を明確に必須要件とした初期の重要判例です。テックジャパン事件最高裁判決における櫻井龍子裁判官の補足意見(以下「櫻井補足意見」)の考え方が明らかに影響を与えており、その後の裁判例にも大きな影響を及ぼしています。
定額残業代をめぐる法的要件が厳格化される流れの転換点となった判決として、実務上極めて重要な意義を持っています。
2.事案
(1) 概要
被告Y社(アクティリンク)は、不動産売買・賃貸・管理等を業とする会社です。原告X1は売買事業部に所属していた従業員、原告X2は当初売買事業部に在籍後、営業部に異動した従業員です。
売買事業部の主な業務は:
– 「テレホンアポイント業務」:リストに沿って勧誘電話をかけ、顧客との面談を設定する業務
– 「顧客面談」:約束を取り付けた顧客と実際に面談する業務
X1らはこれらの業務の管理・指導を行うグループ上長であり、自らも業務を行うこともありました。X1らはY社退職後、未払割増賃金を請求しました。
(2) 定額残業代に関する規程の定め
X1らの賃金は次の3つから構成されていました:
1. 基本給
2. 諸手当(職能手当、管理者手当、役職手当、営業手当、住宅手当、住宅補助手当、通勤手当)
3. 割増賃金(時間外勤務割増賃金、休日勤務割増賃金、深夜勤務割増賃金)
賃金規程13条には以下の定めがありました:
「営業手当は、就業規則15条による時間外労働割増賃金で月30時間相当分として支給する」
(3) 争点
Y社は、「営業手当」は時間外労働手当としての性質を持つと主張し、仮にX1らに何らかの割増賃金が発生するとしても、X1らに支給された営業手当はそれに充当されるため、算定基礎から除外されるべきだと主張しました。
これに対し、X1らは営業手当が時間外労働の対価ではないと反論し、「営業手当が定額残業代として有効か」が争点となりました。
3.判決の内容
(1) 手当型の定額残業代が有効と認められる条件についての判示
「このように他手当の名目による、定額残業代(割増賃金)の支払が許されるためには、①実質的にみて、当該手当が時間外労働の対価としての性格を有しており(以下「第1の条件」という。)、かつ、②当該定額(固定額)が労基法所定の計算方法による額を下回るときは、その差額を当該賃金の支払時期に清算するという合意が存在するか、あるいは少なくとも、そうした取扱いが確立していること(以下「第2の条件」という。)が必要不可欠である」
(2)「第1の条件」(対価要件)についての判示
「この条件における対価性の判断は、当該手当が、①時間外労働に従事した従業員だけを対象に、それらの従業員全員に対し例外なく支給されることが予定されているか、また②時間外労働の対価以外に合理的な支給根拠(支給の趣旨・目的)を見出すことが可能か否かという2つの観点から行うべきものである。」
「X2に関していうと……業務部へ異動になってからは本件営業手当は一切支払われていない。……X2は業務部に異動した後も、少なくとも毎月第2週目以降は何らかの形で時間外労働に従事していたことが認められ……、してみると本件営業手当は、一応、時間外労働に従事した従業員だけを対象としていたものの、かかる従業員全員に対し例外なく支給されることまでは予定されていなかったのではないかという疑いを挟む余地はある。
またY社代表者は、その尋問で、業務部の従業員に対しては本件営業手当が支給されていない理由を尋ねられ、『……営業はいろいろお客さんと会ってお金を使うこともありますし、やはり営業は大変だというのは分かっていますので、そういう意味で、ほかの従業員よりは多く出すということでやっていました。』(略)などと、かえって、この点に関する原告の主張に沿う供述をしていることに加え、……Y社においては、.…・売買事業部の従業員のうち『主任』以上の地位にある者に対し、その営業成績に応じて、本件営業手当の支給それ自体をカットすることまで予定していたことがうかがわれることなどを併せ考慮すると本件営業手当は、時間外労働の対価というよりもむしろ、営業活動に伴う経費の補充ないしは売買事業部従業員に対する一種のインセンティブとして支給されていたものとみるのが自然である。」
(3)「第2の条件」(差額支払合意)についての判示
(X1には毎月30時間以上の時間外労働が発生していたと認められるところ、)「本件賃金規程13条に基づく支給定額(固定額)は、毎月、労基法所定の計算方法による額を下回り、上記第2の要件にいう「差額」の清算を要する事態が発生していたものといわざるを得ない。ところが本件全証拠を検討しても、Y社がX1らに対して上記「差額」の清算を行った形跡は全く認められず、してみると本件営業手当について上記第2の要件にいう「差額」の清算に関する合意が黙示にも成立していたとは認められず、また、そうした清算の取扱いが確立していたともいい難い。」
(4) 結論
「以上によれば本件営業手当は、上記2つの条件をいずれも満たさず、したがって、本件賃金規程13条に基づき、本件営業手当をもって、時間外労働手当とみなすことは許されないものというべきである。
そうすると本件営業手当は、…・・・労基法37条1項にいう「通常の労働時間又は労働日の賃金」に該当し、本件基礎賃金から除外される手当には当たらない。」
4.検討
(1)「第1の条件」(対価要件)について
本判決は、手当が時間外労働の対価と認められるための要件として、2つの重要な視点を提示しました:
1. 対象の限定性:「時間外労働に従事した従業員だけを対象に、それらの従業員全員に対し例外なく支給されること」
2. 目的の特定性:「時間外労働の対価以外に合理的な支給根拠を見出せないこと」
本件では、以下の事実から対価要件を否定しました:
– X2は時間外労働をしていても業務部異動後は営業手当が支給されていなかったこと
– Y社代表者が営業手当を「営業の大変さ」「お客さんと会ってお金を使うこと」への対価と説明していたこと
– 営業成績によって営業手当をカットする運用を予定していたこと
これらの事実から、営業手当は「時間外労働の対価」ではなく「営業活動に伴う経費補充やインセンティブ」と判断されました。
Y社代表者の証言が決定的であり、営業手当が「時間外労働の対価」という認識すらなかったことが明らかになった点が重要です。
(2)「第2の条件」(差額支払合意)について
本判決が重要なのは、「差額支払合意」を独立した必須要件として明確に位置付けた点です。ただし、本判決は差額支払合意が必要な理論的根拠については明確に述べていません。
労働基準法上、定額残業代を超える残業があった場合の差額支払義務は当然に発生するものです。そのため、差額支払合意がなくても、実際には差額の未払いが生じるだけで、定額残業代自体が全て無効になるとは論理的には考えにくいのです。
興味深いことに、同じ裁判官が3ヶ月前に担当した「株式会社乙山事件」(東京地判平24.3.23)では、定額残業代による一部弁済が認められていました。この短期間での判断の変化は、テックジャパン事件最高裁判決の櫻井補足意見の影響と推測されます。
(3) 櫻井補足意見との関係
本判決が示した「差額支払合意」要件は、テックジャパン事件の櫻井補足意見と明らかに共通しています。櫻井補足意見は「10時間を超えて残業が行われた場合には当然その所定の支給日に別途上乗せして残業手当を支給する旨もあらかじめ明らかにされていなければならない」と述べていました。
ただし、櫻井補足意見は【組込型】の定額残業代を前提としていたのに対し、本件は【手当型】の事案です。本判決は、この差異を考慮せずに櫻井補足意見の考え方を【手当型】にも適用した点で、その射程を拡大したといえます。
5.本判決からの留意点
(1) 定額残業代の性格を明確にする
Y社代表者の証言が示すように、会社側が「営業手当」を残業代の趣旨と認識していなかったことが敗因の一つです。定額残業代を導入する際は:
– 時間外労働の対価であることが明確な名称を使用する(「時間外労働手当」「固定残業手当」等)
– 就業規則や労働契約書に明記し、労使双方で「時間外労働の対価」であるという認識を共有する
– 支給対象となる従業員を時間外労働の実態に応じて合理的に設定する
特に、営業成績など時間外労働と関係のない要素で金額が変動する仕組みは避けるべきです。本判決では「営業成績によるカット」が対価性を否定する要素となりました。欠勤日数に応じた割合的減額は問題ありませんが、年齢、勤続年数、業績など労働時間と関係のない要素で変動する設計は危険です。
(2) 差額支払いの仕組みを確立する
本判決以降、「差額支払合意」を要求する判決が続出しています。理論的には疑問もありますが、実務上のリスク回避のためには:
– 就業規則や労働契約書に差額支払条項を明記する
– 実際の労働時間を適切に把握する仕組みを設ける
– 定額残業代を超える時間外労働があった場合は確実に差額を支給する
– 給与明細書にも明確に区分して表示する
これらの対応により、定額残業代の有効性が否定されるリスクを大幅に軽減できます。
定額残業代が無効とされると、定額残業代とされていた部分も含めて全額が割増賃金の算定基礎となり、多額の未払残業代が発生する可能性があります。本判決が示した厳格な要件を満たす制度設計と運用を心がけることが重要です。
これからアクティリンク第二事件について、元の文書の詳細度や意味内容を変えずに、Web記事として読みやすくリライトし、HTML形式でコーディングします。
アクティリンク第二事件(東京地判平24.8.28)【手当型・無効】★☆☆
1.本判決を紹介する意義
本事件は、アクティリンク第一事件の被告であったY社に対して、売買事業部に所属していた別の従業員Xが割増賃金を請求したものです。本判決の特徴は、テックジャパン事件最高裁判決における櫻井補足意見の影響が非常に色濃く表れている点にあります。判決文の規範定立部分からは、櫻井裁判官の考え方がほぼそのまま採用されていることが明確に読み取れます。
2.事案
賃金規程については、アクティリンク第一事件と共通しています。
本件でも、「営業手当」が定額残業代に当たるか否かが争点となりました。
3.判決の内容
(1) 定額残業代の支払が認められる条件についての判示
「このような他の手当を名目としたいわゆる定額残業代の支払が許されるためには、<1>実質的に見て、当該手当が時間外労働の対価としての性格を有していること(対価要件)は勿論、<2>支給時に支給対象の時間外労働の時間数と残業手当の額が労働者に明示され、定額残業代によってまかなわれる残業時間数を超えて残業が行われた場合には別途清算する旨の合意が存在するか、少なくともそうした取扱いが確立していること(差額支払要件)が必要不可欠であるというべきである。」
(2) 対価要件についての判示
「証拠によれば、営業手当は、売買事業部の従業員が顧客と面談する際にかかる諸経費をまかなう趣旨を含んでいたこと、Y社では業務部の従業員も時間外労働に従事しているにもかかわらず、業務部の従業員に営業手当は支払われておらず、これと同趣旨の別の手当が支払われているわけでもないこと等の事実を認めることができる。これらの事実にかんがみれば、営業手当は、営業活動に伴う経費の補充または売買事業部の従業員に対する一種のインセンティブとして支給されていたものとみるのが相当であり、実質的な時間外労働の対価としての性格を有していると認めることはできない。」
(3) 差額支払要件についての判示
「X1らについて、本件賃金規程13条に基づく支給額(30時間分) との差額の清算を要する月が相当程度存在したことになるが、本件全証拠を検討しても、Y社がX1らに対して上記差額の精算を行った形跡を認めることはできない。」
(4) 結論
「以上によれば、本件における営業手当は、上記条件<1>及び<2>のいずれも満たさないことが明らかであるから、本件賃金規程13条の存在のみによってこれを定額残業代とみなすことはできない。したがって、営業手当は、営業活動に伴う経費の補充または売買事業部の従業員に対する一種のインセンティブとして、労基法37条1項にいう「通常の労働時間又は労働日の賃金」に該当するというべきである。」
4.検討
(1) 櫻井補足意見の強い影響
本判決の清算要件は、テックジャパン事件最高裁判決における櫻井補足意見とほぼ同一の文言を用いており、その影響を強く受けていることが明白です。
櫻井補足意見では「支給時に支給対象の時間外労働の時間数と残業手当の額が労働者に明示され、10時間を超えて残業が行われた場合には別途上乗せして残業手当を支給する旨もあらかじめ明らかにされていなければならない」と述べられていました。
本判決はこの考え方をほぼそのまま採用し、時間外労働の時間数の明示まで求める厳格な基準を示しています。
(2) 問題点:用語の曖昧さと適用範囲の違い
本判決には2つの問題点があります:
用語の曖昧さ:「支給対象の時間外労働の時間数」という文言の意味が不明確です。定額残業代が対価とする時間数を指すのか、実際に行われた時間外労働時間を指すのかが判然としません。
事案の性質の違い:櫻井補足意見は基本給組込型の事案に関するものでしたが、本件は手当型の事案です。問題状況が異なるにもかかわらず、同じ基準を適用している点に疑問があります。
(3) 差額支払合意の位置づけ
本判決は差額支払合意を必要条件としていますが、理論的には疑問が残ります。労働基準法上、差額の支払義務は法律から当然に発生するものであり、合意の有無にかかわらず使用者には支払義務があります。
差額支払合意がなくても定額残業代自体は有効と解すべきであり、単に差額の支払いがないという法律違反が発生するだけと考えるのが論理的です。
5.本判決からの実務上の留意点
(1) 対価性の明確化
定額残業代を手当として支給する場合は:
手当の名称を時間外労働との関連が明確なものにする(「時間外勤務手当」「固定残業手当」等)
給与規程や契約書に明確に時間外労働の対価である旨を記載する
他の目的(経費補填やインセンティブ)と混同しない
時間外労働を行う部署・職種に限定して支給する
(2) 時間数と金額の明示
本判決は時間数の明示も必須と解しています。理論的には金額の明示だけでも足りると考えられますが、リスク回避の観点から:
定額残業代が何時間分の時間外労働の対価か明示する
金額と時間数の両方を労働契約書に明記する
給与明細書にも時間数と金額を記載する
実際の時間外労働時間を正確に把握する体制を整える
(3) 差額支払いの仕組み確立
本判決の影響から、裁判所が差額支払いを重視する傾向は続いています:
就業規則や労働契約書に差額支払条項を明記する
実際に超過した場合は必ず差額を支払う運用を徹底する
差額支払の実績を残す(給与明細への明確な記載など)
これらの対応により、定額残業代が無効とされるリスクを軽減できます。定額残業代が無効とされると、その全額が割増賃金の算定基礎に算入され、多額の追加支払いが発生する可能性があるため、慎重な制度設計と運用が必要です。
イーライフ事件(東京地判平25.2.28)【手当型・無効】★☆☆
1.本判決を紹介する意義
本判決は、定額残業代の有効性判断において極めて詳細かつ厳格な規範を定立した重要事例です。定額残業代に関する「対価要件」「明確区分性要件」「差額支払合意要件」を明確に整理し、各要件の具体的内容を示しています。
本判決も、テックジャパン事件最高裁判決における櫻井補足意見の影響が非常に色濃く表れています。
2.事案
(1) 概要
被告Y社(イーライフ)は、ポータルサイトの運営やIT関連事業などを行う会社です。原告Xは、平成19年3月にY社の東京事業部に異動し、同時に給与体系が歩合給制から年俸制に変更されました。
Y社が競業行為への加担を理由にXを懲戒解雇したところ、Xが不支給とされた退職金および未払割増賃金の支払いを求めて提訴しました。
(2) 定額残業代に関する規程の定め
Y社の賃金規程には以下の定めがありました:
「会社は、営業社員について本規程第15条の超過勤務手当に代えて、精勤手当を定額で支給する。なお、超過勤務手当が精勤手当を超える場合には、その差額を支給するものとする」(賃金規程13条)
時間外勤務手当の計算方法も規定されていました:
「基本給/その年度における1カ月の平均所定労働時間×時間外労働時間数×1.25」(賃金規程15条)
(3) 争点
Xに支給されていた「精勤手当」が定額残業代としての性格を有し、割増賃金の算定基礎から除外されるかが主な争点となりました。
Xは、自身は営業職員ではないため賃金規程13条は適用されず、精勤手当が残業代の趣旨だとの説明も受けていないと主張しました。これに対しY社は、規程の「営業社員」は記載ミスで「年俸制の社員」を含むとし、精勤手当の趣旨についてXに説明して了解を得ていたと反論しました。
3.判決の内容
(1) 給与規程の適用と合意の有無
裁判所は、Y社の「規程に記載ミスがあった」との主張を認めず、年俸制のXには給与規程13条は適用されないと判断しました。また、精勤手当が残業代の趣旨であるとの説明をXに行い、了解を得ていたというY社の主張も退け、そのような合意(「本件みなし残業合意」)は成立していないと結論付けました。
(2) 定額残業代の有効要件に関する詳細な規範の定立
判決は、仮定的判断として、合意があったとしても有効と言えるかを検討し、以下のような厳格な規範を定立しました:
「他手当の名目(精勤手当)による定額残業代の支払に関する個別合意は、Y社の基本的な賃金構成を修正するものである上、安易に容認すれば割増賃金制度によって時間外労働を抑制しようとする労基法の趣旨が没却される。そうした合意が有効とされるためには、
<1>当該手当が実質的に時間外労働の対価としての性格を有していること(要件a)
<2>定額残業代として労基法所定の額が支払われているか判定できるよう、その約定(合意)の中に明確な指標が存在していること(要件b)
<3>当該定額(固定額)が労基法所定の額を下回るときは、その差額を当該賃金の支払時期に精算するという合意が存在するか、あるいは少なくとも、そうした取扱いが確立していること(要件c)
が必要不可欠である。」
(3) 各要件の具体的内容と本件への当てはめ
「要件a」(対価要件)について:
「要件aを満たすには、少なくとも当該手当が、①時間外労働に従事した従業員だけを対象に支給され、しかも②時間外労働の対価以外に合理的な支給根拠(支給の趣旨・目的)を見出すことができないことが必要である」
本件では、「精勤手当の支給額がXの年齢、勤続年数、Y社の業績等により全請求期間中に数回変動している」ことから、「時間外労働の対価としての性質以外のものが含まれており」、要件aを満たさないと判断しました。
「要件b」(明確区分性)について:
「要件bを満たすには、少なくとも当該支給額に固定性(定額制)が認められ、かつ、その額が何時間分の時間外労働に相当するのかが指標として明確にされていることが必要である」
本件では、精勤手当は「1年間に数回も変動しており、その幅も小さくなく固定性(定額制)に疑問があるばかりか、合意中に当該支給額が何時間分の時間外労働に相当するかを明確にする指標を見出すことはできない」として、要件bも満たさないと判断しました。
「要件c」(差額精算)について:
「要件cを満たすには、労基法所定の割増賃金との差額精算の合意ないしはその取扱いが確立していることで足りる」としたうえで、本件では「差額精算の合意ないし取扱いが存在したことを認めるに足る証拠はない」として、要件cも満たさないと結論付けました。
(4) 結論と付加金
以上から、仮にXとY社の間に本件みなし残業合意が成立していたとしても、その合意は上記各要件を満たさず無効であると判断しました。
また、付加金について「特別の事情が認められない限り、認定された未払金と同額の割増賃金の額の支払を命じるべき」として、認容額と同額の付加金の支払いも命じました。
4.検討
(1) 明確区分性要件の厳格化
本判決は、明確区分性の要件について、定額残業代の金額だけでなく「何時間分の時間外労働に相当するのか」の明示まで必要とする厳格な基準を示しています。
しかし、なぜ金額だけでなく時間数の明示までもが必要となるのか、その理由については明確に述べられていません。判決が述べるように、明確区分性が求められる趣旨は「定額残業代として労基法所定の額が支払われているか否かを判定できるようにするため」であれば、金額が明示されていれば労基法所定の計算と比較可能であり、時間数まで明示する必要性には論理的な根拠が薄いと考えられます。したがって、時間数の明示までは必要ないと考えられます。
(2) 対価要件の厳格な定義
本判決は、対価要件の充足条件として、①時間外労働に従事した従業員だけを対象とすること、②時間外労働の対価以外の支給根拠がないことという2点を挙げています。
しかし、定額残業代は、恒常的な時間外労働が見込まれる労働者に支給されるものであって、実際に時間外労働に従事した労働者にその対象を限定する必要はないと考えられます。また、特に注目すべきは、従業員の年齢、勤続年数、会社業績等に応じて金額が変動する仕組みが対価性を否定する要素とされた点です。実務上、多くの企業が年齢や勤続年数に応じて手当額を変動させる仕組みを採用しており、この判断基準は大きな影響があります。このような事情がある場合は、時間外労働の対価としての性質を否定される要素の一つとなることは留意する必要があります。
(3) 差額支払合意要件の位置づけ
本判決は「要件c」として差額支払合意を明確に必須要件として位置づけています。しかし、労基法上、差額の支払義務は法律から当然に発生するものであり、合意の有無にかかわらず発生します。
理論的には、差額支払合意がなくとも定額残業代自体は有効であり、単に差額の未払いという法律違反が発生するだけと考えるべきです。差額支払合意を独立の要件とする点には疑問が残ります。
(4) 付加金の判断基準
本判決は「特別の事情がない限り同一額の付加金を命じるべき」という原則的な判断基準を示しています。しかし、労基法114条は付加金支払の命令自体にも裁量を認めており、その金額についても裁量があると解するのが自然です。
付加金は制裁的・懲罰的性格を持つものであり、違反の程度や態様、事情によって金額を調整すべきとの考え方もあります。本判決の基準は厳格すぎるとの批判もあります。
5.本判決からの実務上の留意点
(1) 時間数の明示
本判決は、定額残業代について金額だけでなく対象時間数も明示すべきとしています。理論的には必要ないと考えられる部分もありますが、リスク回避の観点からは:
– 定額残業代が何時間分の時間外労働の対価かを就業規則や労働契約書に明記する
– 給与明細書にも時間数を記載する
– 雇入れ時や制度導入時に、時間数と金額を明確に説明する
(2) 支給基準と変動要素への注意
本判決では、年齢、勤続年数、会社業績による金額変動が対価性を否定する要素となりました:
– 定額残業代は労働時間に関連する要素だけで金額を決定する
– 年齢や勤続年数による金額変動は避ける
– 会社業績による変動も避ける
– 固定的な金額設定を基本とする
– 欠勤による日割減額など労働時間に関連した調整のみを行う
(3) 対象者の限定
本判決は「時間外労働に従事した従業員だけを対象」とすべきとしています:
– 事前に労働時間実態調査を行い、時間外労働が恒常的に発生する部署・職種を特定する
– 調査結果に基づいて対象者を合理的に限定する
– 調査資料は保存し、定額残業代導入の合理性の根拠資料とする
– 時間外労働が発生しない従業員には支給しない明確な区分を行う
(4) 差額支払いの徹底
差額支払合意の有無に関わらず、実際に差額支払いを行う体制を整備することが重要です:
– 労働時間管理を徹底する
– 定額を超える時間外労働があった場合は確実に差額を支給する
– 給与明細書に明確に区分して記載する
– 差額支払いの実績を記録として残す
これらの対応により、定額残業代制度が無効とされるリスクを最小化できます。本判決が示した厳格な要件に沿った制度設計と運用が、リスク管理の鍵となります。
第4章:テックジャパン事件以降の判断の多様化と個別論点の深化(平成24年~平成29年)
テックジャパン事件最高裁判決、特に櫻井龍子裁判官の補足意見は、その後の下級審における固定残業代の有効性判断に大きな影響を与えました。しかし、その影響の受け止め方や具体的な事案への適用においては、裁判所ごとに判断が分かれる場面も見られ、固定残業代をめぐる法的論点はさらに多様化・深化していくことになります。
この章では、テックジャパン事件以降に示された注目すべき裁判例を、主要なテーマや争点ごとに整理しつつ、引き続き時系列に沿って概観していきます。「差額支払合意・実績」の要否に加え、「時間数・金額の相当性」や「明確区分性の具体的なあり方」など、より踏み込んだ論点についての司法判断を見ていきましょう。
ワークフロンティア事件(東京地判平24.9.4)【組込型・有効】★★☆
1.本判決を紹介する意義
本判決は、差額支払実績がなかったにもかかわらず定額残業代の合意を有効とした重要事例です。テックジャパン事件最高裁判決以降、差額支払合意を厳格に要求する傾向が強まる中、本件では当事者の合理的意思解釈を重視し、柔軟な判断を示しました。
「差額支払合意」が独立した要件ではないという理論的に妥当な立場を採用した判例として、実務上大きな意義を持っています。また、過去の未払残業代の清算についての有効な合意の成立要件も示しており、定額残業代制度の導入時の実務にとって参考になります。
2.事案
(1) 概要
被告Y社は、廃棄物収集・運搬を主たる業とする会社です。原告X1~X4らの基本給は月額28万5,000円~30万7,000円で、労働契約書には「基本給○万円(残業代は月額給与に含む)」と記載されていました。
労働基準監督署から割増賃金の未払いを指摘されたため、Y社は将来に向けて賃金体系を整備しました。基本給の総額を維持しつつ、その一部に月45時間分の「固定割増賃金」を組み込んで支払うこととし、全従業員と新たな労働条件通知書(新労働契約書)で合意しました。
その後、原告X5~X9らが入社し、同様の合意がなされました。さらに、従業員の基本給に「固定割増賃金」を一部含ませることがある旨の新賃金規程も設けられました。
しかし、制度導入後も月45時間を超える時間外労働があった場合に、差額支払いが実際に行われた実績はありませんでした。これを受け、Xらが各種割増賃金の支払いを求めて提訴しました。
(2) 定額残業代に関する規程の定め
新労働契約書(労働条件通知書)には、基本給及び定額残業代について以下のように定められていました:
「基本給29万2,000円(※時間外労働45時間分の固定割増賃金7万1,544円を含む)」
また、差額支払いについては、「時間外労働に対する割増賃金額が固定割増賃金を超えた場合にその差額を『超過勤務手当』として支給する」旨の規定も置かれていました。
新賃金規程にも、「管理監督者以外の従業員の基本給には、時間外等労働に対する一定の割増賃金を固定割増賃金として一部含ませることがある」旨が定められていました。
(3) 争点
月45時間を超える時間外労働があっても、実際には固定割増賃金との差額が支払われていなかったことから、Xらは「Y社には差額を支払う意思がなく、固定割増賃金の定めは無効である」と主張しました。定額残業代の有効性が主な争点となりました。
3.判決の内容
(1) 定額残業代の合意の有効性
「①各労働条件通知書の記載自体から明らかなとおり、各基本給に含まれる固定割増賃金は時間外労働45時間分にすぎず、それを超える長時間の残業がされた場合等には、基本給では消化しきれない超過割増賃金が発生することは当然の前提とされている。
②そして、基本給の他には割増賃金を支払わないという従前の取扱いを改め、固定割増賃金制度を導入するべくXらとの個別合意が図られたという本件の経緯に照らし、各労働条件通知書に示された合意内容を合理的に解釈すれば、明文の記載はなくとも、上記のように超過割増賃金が発生する場合にY社が差額支払義務を負うことはむしろ当然のこととして当事者間で合意されていると解すべきであり、現に、各労働条件通知書には『超過勤務手当』として差額を支給する旨の規定も存するところであるから、Xらの上記主張は採用できない。
③なお、実際には、これまで固定割増賃金を超える精算がなされたことはないものと認められるが、その点は付加金において考慮すれば足り、当事者間の合理的意思解釈としては、上記のように解するほかはないものと言うべきである。」
(2) 過去の未払残業代清算合意の有効性
本判決は、Y社が過去の残業代について、X1~X3を含めた従業員に支払いを行い、書面で「受領した残業代以外に賃金債権はない」旨の確認を取ったことについても判断しています。
裁判所は、この書面による確認を「仮に未払残業代債権が存在するとしてもそれを放棄する旨の意思表示」と解し、Y社の社労士より労基署の是正勧告への対応として説明がなされた上でのことであったことなどから、「自由な意思によるものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在し、残業代放棄の意思表示として有効」と判断しました。
4.検討
(1) 差額支払要件に関する柔軟な判断
本判決の最大の特徴は、差額支払いの実績がなくても定額残業代の合意を有効と認めた点です。判決は、次の理由から差額支払合意が存在すると判断しました:
1. 労働条件通知書の記載から「超過割増賃金が発生することは当然の前提」であると認められる
2. 従前の取扱いを改め定額残業代制度を導入した経緯から、差額支払義務を負うことは「当然のこととして合意されている」と解釈できる
3. 労働条件通知書に「超過勤務手当」の規定が存在する
特に重要なのは、差額支払実績がないことについて「付加金において考慮すれば足り、当事者間の合理的意思解釈に影響しない」と明確に述べている点です。これは、差額支払実績の有無を定額残業代の合意の有効性判断から切り離す立場を明確にしたものです。
(2) 「差額支払合意」の位置づけ
本判決は、「第3要件」(差額支払合意・実績)を独立した有効要件とは解していません。これは高知県観光事件最高裁判決に沿った妥当な判断です。
定額残業代の有効性は、通常賃金部分と割増賃金部分が明確に区分できるか(第1要件)、定額残業代として支給する趣旨と認められるか(第2要件)についての契約解釈の問題であり、差額支払の合意や実績は、これらの要件充足の間接事実にすぎないと考えられます。
本判決が前記②で述べているように、「差額支払義務を負うことは当然のこと」として合意されていると解釈するのが合理的であり、明文の規定がなくても差額支払合意の存在を認めるべきとの考え方は、多くの事案に一般的に妥当するものと考えられます。
(3) 過去の未払残業代清算合意の有効性
本判決は、過去の未払残業代についての清算合意の有効要件も示しています。具体的には:
– 労働時間数も含めた計算根拠の説明がなされていること
– 放棄することの法的意味についての説明があること
– 労働者の自由な意思によるものであること
これらの条件を満たせば、過去の残業代債権を放棄する合意も有効となる可能性があります。これは、定額残業代制度の導入と同時に過去の未払残業代問題も解決しようとする企業にとって参考になる判断です。
5.本判決からの実務上の留意点
(1) 合理的な定額残業代制度の設計
本判決は「差額支払実績」を重視しない判断を示していますが、リスク管理の観点からは:
– 就業規則や労働契約書に差額支払条項を明記する
– 実際の労働時間を適切に把握する
– 定額残業代を超える時間外労働があった場合は確実に差額を支給する
これらの対応を行うことが依然として重要です。
特に、本判決では差額支払実績がないことを理由に付加金が認められている点に注意が必要です。
(2) 制度導入時の過去の清算
定額残業代制度を導入する際に、過去の未払残業代問題も解決するには:
– 労働時間の実態を正確に把握し、未払残業代を適正に計算する
– 計算根拠を明示し、十分な説明を行う
– 清算合意書には「残業代を受領したこと」と「その他の賃金債権はないことを確認する」旨を明記する
– 労働者の自由な意思に基づく合意であることを確保する(強制でないこと)
– 合意のプロセスと説明内容を記録として残す
これらの対応により、将来の紛争リスクを低減できます。
(3) 賃金規程・就業規則の変更手続き
本件では、定額残業代制度の導入が就業規則の不利益変更に当たるかも争われました:
– 定額残業代の導入は通常賃金部分の減少を伴うため、「不利益変更」と解される可能性がある
– 変更の合理性(必要性、内容の相当性、代償措置、労働者への説明等)を確保する
– 個別同意を取得するか、就業規則変更の場合は意見聴取手続きを適正に行う
– 制度の趣旨や必要性を十分に説明し、理解を得る努力をする
トレーダー愛事件(京都地判平24.10.16)【手当型・無効】★☆☆
1.本判決を紹介する意義
本判決は、定額残業代の対価要件を判断する際に「賃金バランス」という新たな視点を重視した判例です。明確区分性が満たされており、規程上は差額精算の定めも置かれていたにもかかわらず、通常賃金部分と定額残業代部分の比率に着目し、定額残業代部分が不自然に高額であることを理由に対価要件を否定しました。
定額残業代制度が「残業代支払いを免れる便法」として機能することを防ぐための判断枠組みを示した点で、実務上重要な意義を持ちます。本判決は、形式的に要件を満たすだけでなく、定額残業代制度の実質的合理性が問われることを告げるものといえます。
2.事案
(1) 概要
被告Y社(トレーダー愛)は、冠婚葬祭やそれに関連する諸分野を中心に事業を展開する会社です。原告Xは、京都市内のホテルでフロント担当として勤務していた従業員で、当該ホテルがY社に買収された後も、Y社との労働契約でホテル勤務を継続していました。
Xの月所定労働時間は172.5時間で、月例給与として基本給14万円、成果給13万円、宿直1回につき3,000円の宿日直手当が支払われていました。この賃金構成の決定過程では、Y社の担当者が「従来のXの給与額27万円は保障するが、内訳は基本給14万円、成果給13万円とする」と説明し、Xがこれに合意したという経緯がありました。
Xは退職後、Y社に対して未払割増賃金の支払いを求めました。
(2) 給与規程の定め
Y社の給与規程には以下のような定めがありました:
「第3条 給与の体系は次のとおりとする。
1. 基準内賃金(時間外労働の基準額に含まれる賃金)
①基本給(基本給表による)
②役割給(職位に応じて設定、役割給表による)
2. 基準外賃金(時間外労働の基準額に含まれない賃金)
①通勤費(通勤方法・通勤距離に応じて支給する)
②役割業務手当(時間外手当に相当)
③成果給(前年度の成果および管轄業務に応じて設定、時間外手当に相当)
④成績手当(時間外手当に相当)
各事業部の「職務手当規程」による。
⑤勤務手当・営業手当・集金地域手当(時間外手当に相当)
各事業部の「職務手当規程」による。
⑥繁忙手当(時間外手当に相当)
施行数が前年度平均の25%以上に及ぶ場合、または新店舗開設により時間換算給与の増額が見込まれる場合、施行数増加分の勤務手当として支給する。
⑦調整手当(時間外手当と、成果給・成績手当・勤務手当・繁忙手当との差額を支給)」
成果給等と時間外手当の関係について、以下の定めもありました:
「成果給と成績手当及び勤務手当・繁忙手当の合計額が、時間外労働に対する手当の合計額より多い場合は、成果給と成績手当及び勤務手当・繁忙手当を支給する。ただし、成果給と成績手当及び勤務手当・繁忙手当の合計額が、時間外労働に対する手当の合計額を下回る場合は、差額を調整手当として成績手当にて支給する。」
さらに第15条には、「成果主義は、労働時間を短縮し、業務を効率よく遂行し、目標の業績をあげることを推進するものであり、効率の悪い長時間労働を防止することを目的とするものである」との規定もありました。
(3) 争点
Y社は、給与規程3条に基づき、成果給が時間外手当として割増賃金の基礎となる賃金から除外されると主張しました。また、就業規則に定めのない宿日直手当についても、時間外手当に当たると主張したため、成果給及び宿日直手当が時間外手当に当たるか否かが争点となりました。
3.判決の内容
(1) 成果給についての判断
ア.基本給と時間外手当の比率に関する判断
「ホテルのフロント業務は時間内と時間外で業務が異なるものではないことからすると、所定内労働の賃金と時間外手当で労働単価に著しい差がある場合には、その賃金体系は合理性を欠いており、両者の割り振りが不相当ということになる。
Yの賃金体系では、時間外労働の時給が所定時間内労働の時給の倍となっていることから、Yの賃金体系は、基本給と成果給とのバランスをあまりにも欠いたものであり、成果給に基本給に相当する部分を含んでいると解さざるを得ない。」
イ.成果給の性質
「成果給は前年度の成果に応じて人事考課によって決められるのに対し、時間外労働に対する対価である時間外手当は、労働時間に比例して支払わなければならないものであり、前年度の成果に応じて決まるような性質のものではないから、Yは、性質の異なるものを成果給の中に混在させている。」
ウ.基本給の設定
「Yにおける基本給は、ほぼ最低賃金に合わせて設定されており、それ以外の賃金はすべて時間外手当とすることによって、よほど長時間の労働をしない限り、定額の時間外手当のほかに時間外手当は発生しない仕組みになっている。」
エ.給与額の決定過程
「Yにおいて、時間外手当について、Yが求める成果の達成にどれほどの時間外労働を要するかなどの検討をした様子は全くなく、単純に最低賃金時間額を上回って万単位で最も低い金額を基本給とし、従前の賃金27万円に達するまでの差額を定額の時間外手当に割り振ったものである。」
オ.小括
「業務内容が異ならないにもかかわらず、基本給と時間外手当とで時間単価に著しい差を設けることは本来あり得ず、Yの給与体系は、時間外手当を支払わないための便法ともいえるものであって、成果給の中に基本給に相当する部分が含まれていると評価するのが相当である。」
「以上のとおり、Yの賃金体系は不合理なものであり、成果給(時間外手当)の中に基本給の部分も含まれていると解するのが相当である。そうすると、成果給がすべて時間外手当であるということはできず、成果給の中に基本給と時間外手当が混在しているということができるのであって、成果給は割増賃金計算の基礎賃金に含まれるとともに、時間外手当を支払った時のYの主張は失当である。」
(2) 宿日直手当についての判断
「宿日直手当についても、(1)と同様のことがいえ、宿日直手当についてすべて時間外手当であり、時間外手当として支払った旨のYの主張は失当である。」
4.検討
(1) 形式的要件具備と実質的合理性
本件においては、給与規程上、成果給は時間外手当に当たると明記されており、「調整手当」により差額精算する定めも存在しました。形式的には第1要件(明確区分性)と第3要件(差額支払合意)を満たしているようにも見えます。
しかし、本判決は形式的な要件充足に留まらず、賃金体系の実質的合理性を詳細に検討し、以下の理由から成果給の時間外労働の対価としての性格を否定しました:
1. 時間内・時間外で労働内容が同じなのに、時給単価に倍以上の差があることの不合理性
2. 成果給が「前年度の成績」に応じて決定される性質と時間外手当の性質の相違
3. 基本給を最低賃金ギリギリに設定し、長時間労働しなければ差額が発生しない仕組み
4. 時間外労働の実態調査なしに、単に「従前給与額−最低水準の基本給」という形で成果給額を決定した経緯
これらの事情から、給与体系全体が「時間外手当を支払わないための便法」と評価されました。
(2) 「賃金バランス」という新しい視点
本判決の最大の特徴は、「所定内労働の賃金と時間外手当で労働単価に著しい差がある場合には、賃金体系は合理性を欠く」という判断基準を示した点です。
具体的には、本件では基本給が14万円、成果給が13万円という構成で、成果給(定額残業代)が基本給とほぼ同額という極端なケースでした。これにより、時間外労働の時給単価が所定時間内労働の時給単価の約2倍になる不自然な状況が生じていました。
労働の内容が時間内・時間外で変わらないのであれば、賃金単価に著しい差が生じることは不自然であるという考え方は、時給単価の観点から定額残業代の合理性を判断する新たな視点として重要です。
(3) 定額残業代制度の意図・設計プロセスの重視
本判決は、Y社が「時間外労働の実態調査」や「成果達成に要する時間外労働の検討」を行った形跡がなく、単に最低賃金レベルの基本給と従前給与の差額を定額残業代に振り分けただけという設計プロセスも問題視しています。
このことは、定額残業代制度の導入・設計に際して、労働時間の実態調査や合理的な時間外労働時間の見積もりが重要であることを示唆しています。単なる「賃金操作」ではなく、実態に基づいた制度設計が求められているといえます。
5.本判決からの実務上の留意点
(1) 通常賃金と定額残業代のバランスに注意
本判決から最も重要な教訓は、通常賃金部分と定額残業代部分の比率に注意すべきということです:
– 定額残業代が通常賃金に比して不自然に高額にならないよう設計する
– 時間内と時間外の時給単価の差が著しく大きくならないよう注意する
– 基本給を最低賃金ギリギリに設定するような極端な賃金設計を避ける
特に、本件では基本給と成果給がほぼ同額という極端なケースでしたが、定額残業代が基本給の半分を超えるような場合は注意が必要です。
(2) 労働時間実態調査の実施と記録
定額残業代制度を導入する際は:
– 事前に時間外労働の実態調査を行い、平均的な時間外労働時間を把握する
– どの程度の時間外労働が業務遂行上必要かを合理的に検討する
– 調査・検討の過程と結果を文書化して保存する
– 実態調査に基づいて定額残業代の時間数と金額を決定する
これにより、定額残業代制度が「時間外手当を支払わないための便法」ではなく、実態に即した合理的な制度であることを立証できます。
(3) 定額残業代の性質と支給基準の整合性
本判決では、成果給が「前年度の成果に応じて人事考課によって決められる」性質と時間外手当の性質の不一致も指摘されています:
– 定額残業代の名称は時間外労働との関連性が明確なものにする(「時間外労働手当」「固定残業手当」等)
– 定額残業代の金額決定基準は労働時間に関連する要素のみとする
– 年齢、勤続年数、成果、業績など時間外労働と関係のない要素で変動する仕組みは避ける
– 就業規則や労働契約書に定額残業代の趣旨と計算方法を明記する
(4) 差額支払いの運用
給与規程上は差額精算の規定(「調整手当」)があっても、実際に支払われていなければ、制度全体の合理性が疑われる可能性があります:
– 労働時間管理を徹底し、実態を正確に把握する
– 定額残業代を超える時間外労働があった場合は確実に差額を支給する
– 差額支払いの実績と記録を残す
– 給与明細書に明確に区分して記載する
ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル事件(札幌高判平24.10.19)【手当型・一部有効】★★☆
1.本判決を紹介する意義
本判決は、差額支払実績がない定額残業代制度について「全部無効」ではなく「一部有効」と判断した事例です。定額残業代の対象時間数が95時間と長大だったにもかかわらず、45時間分に限定して有効と認めるという柔軟な解決策を示しました。
2.事案
(1) 概要
被控訴人X(一審原告)と控訴人Y社(一審被告・ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル)は、入社時に「基本賃金年額624万2,300円(月額52万0,191円)」との労働契約を締結しました。当初、定額残業代についての合意はありませんでした。
その後、賃金は減額され、「基本賃金年額500万円(月額賃金37万9,200円+賞与)」となりました。Y社の主張によれば、この月額賃金には基本給と職務手当が含まれていましたが、判決では具体的な説明がなされていないと認定されています。
さらに賃金が減額され、月額で「基本給22万4,800円、職務手当15万4,400円」が支給されるようになり、Xはその旨が記載された書面に署名捺印してY社に提出しました。同書面には「職務手当(割増賃金)15万4,400円」と記載されていました。
Y社は、残業代については職務手当以外には深夜割増賃金のみを支払っていました。Xは退職後、各種割増賃金の支払いを求めて提訴しました。
一審判決は、職務手当は時間外労働45時間分の限度で定額残業代と認められるとして、X主張の毎月の時間外労働時間から45時間を差し引いて算出した割増賃金の支払いを命じました。これに対し、Y社が控訴しました。
(2) 定額残業代に関する規程の定め
労働契約書(労働条件確認書):
「基本給22万4,800円、職務手当(割増賃金)15万4,400円」と記載
賃金規程:
「(26条)
1項 所定労働時間を超えて勤務する時間及び深夜労働に対し、毎月一定額をみなし時間外手当てとして職務手当を支給することがある。
2項 職務手当の支給額については、職種・職責等に応じて各人毎に決定する。
3項 職務手当は、管理・監督の職にある者について深夜労働分のみを支給する。」
(3) 争点
Y社は、次の計算式に基づき、職務手当は1か月95時間分の時間外労働に対する割増賃金であると主張しましたが、Xはこれを争いました。
(Y社主張の計算式)
22万4,800円÷173.33時間×1.25=1,622円
1,622円×95時間=15万4,400円(職務手当の額)
主な争点は、職務手当がY社主張のとおり95時間分の定額残業代として認められるか否かでした。
3.判決の内容
(1) 職務手当受給合意の解釈
「Y社は、本件職務手当が95時間分の時間外賃金であると主張する。
しかしながら、①賃金規程26条1項では、職務手当が深夜勤務(割増率25パーセント)の対価も含むとされているのに対し、Y社主張の計算は、深夜勤務を考慮していない点で上記賃金規程と整合していない。
②そもそもY社は本件職務手当とは別に、深夜勤務手当をXに支払っており、本件職務手当が賃金規程にいう「職務手当」と同一のものなのかも疑問である。
しかも、Y社は③95時間を超える残業が生じても、これに対して全く時間外賃金を支払っていない④Xも本件職務手当以外に時間外賃金が支払われるとは考えていなかったというのである。
上記のような事情からすれば、⑤本件職務手当の受給に関する合意は、時間外労働が何時間発生したとしても定額時間外賃金以外には時間外賃金を支払わないという趣旨で定額時間外賃金を受給する旨の合意(以下、この合意を「無限定な定額時間外賃金に関する合意」という)であったものと解される⑥このような無限定な定額時間外賃金に関する合意は、強行法規たる労基法37条以下の規定の適用を潜脱する違法なものである」
(2) 無限定な定額時間外賃金に関する合意は全部無効か
「無限定な定額時間外賃金に関する合意は、強行法規たる労基法37条以下の規定の適用を潜脱する違法なものであるから、これを全部無効であるとした上で、職務手当の全額を基礎賃金に算入することも考えられる。
しかしながら、⑦ある合意が強行法規に反しているとしても、当該合意を強行法規に反しない意味内容に解することが当事者の合理的意思に合致する場合には、そのように限定解釈をするのが相当であって、強行法規に反する合意を直ちに全面的に無効なものと解するのは相当ではない。
⑧したがって、本件職務手当に関する合意は、一定時間の残業に対する時間外賃金を定額時間外賃金の形で支払う旨の合意であると解するのが相当である。」
(3) 職務手当は何時間分の時間外労働割増賃金として合意されたか
「定額の時間外賃金が合意されると、その支払がされる分の時間外労働を使用者から要求された場合、労働者は、法的な義務として時間外労働をせざるを得ないと考えられる。すなわち、⑨定額時間外賃金の合意は、時間外労働をすべき私法上の義務(使用者から見れば権利)を定める合意を含むものということができる。
ところで、⑩労基法36条の趣旨は就業規則や労働契約の解釈指針とすべきである。
そうすると、⑪本件職務手当の受給合意について、これを労基法36条の上限として周知されている月45時間(昭和57年労働省告示69号・平成41労働省告示第72号により示されたもの)を超えて具体的な時間外労働義務を発生させるものと解釈するのは相当ではない。
⑫本件職務手当を95時間分の時間外賃金であると解釈すると、Xは95時間分の時間外労働義務を負うことになるものと解されるが、労基法36条の規定を無意味なものとするばかりでなく、安全配慮義務に違反し公序良俗に反するおそれさえあるというべきである(月45時間以上の時間外労働の長期継続が健康を害するおそれがあることを指摘する厚生労働省労働基準局長の通達基発第1063号参照)
以上のとおりであるから、⑬本件職務手当は、45時間分の通常残業の対価として合意され、そのようなものとして支払われたものと認めるのが相当である。」
4.検討
(1) 「無限定な定額時間外賃金に関する合意」の認定
本判決は、以下の事情から「無限定な定額時間外賃金に関する合意」(時間外労働が何時間発生しても定額残業代以外には支払わないという合意)があったと認定しました:
1. 賃金規程と計算式の不整合:規程では深夜勤務の対価も含むとされているが、Y社の計算式では考慮されていない
2. 別途深夜手当の支給:職務手当とは別に深夜勤務手当が支払われていた実態
3. 95時間超の時間外労働に対する不払い:実際に超過があっても差額支払いがなかった
4. 当事者の認識:Xも職務手当以外に時間外賃金が支払われるとは考えていなかった
ただし、「無限定な定額時間外賃金に関する合意」の認定については疑問があります。特に、差額支払実績がないことから直ちにそのような合意があったと認定することは論理的飛躍があると考えられます。差額支払いがない事実自体は、単に割増賃金に未払いがあることを意味するにすぎず、「いかなる場合も支払わない」という合意の存在を直ちに導くものではないからです。
(2) 合意の一部有効性判断
本判決の画期的な点は、「無限定な定額時間外賃金に関する合意」を強行法規違反で違法としながらも、「全部無効」ではなく「限定解釈による一部有効」という柔軟な解決を示したことです。
判決は、「当事者の合理的意思に合致する場合には、強行法規に反しない意味内容に限定解釈するのが相当」という一般原則を示し、「一定時間の残業に対する時間外賃金を定額で支払う合意」として有効性を認めました。これは、当事者の意思を可能な限り尊重する契約解釈の姿勢を示すものです。
(3) 定額残業代と労働時間上限規制の関係
本判決の最も重要な貢献は、定額残業代制度と労働時間の上限規制との関係性を明確に示した点です。判決は次の重要な考え方を示しています:
1. 定額残業代の合意は「時間外労働義務」の合意を含む:定額残業代は単なる支払方法ではなく、その時間分の残業を労働者が「義務」として行うことを含意する
2. 労基法36条(36協定)の趣旨は労働契約解釈の指針となる:法定上限を超える時間外労働義務を含む契約解釈は相当でない
3. 月45時間を超える時間外労働義務は安全配慮義務違反・公序良俗違反のおそれ:健康確保の観点から月45時間を超える時間外労働を「義務」とすべきでない
こうした考えに基づき、95時間分とされていた定額残業代を45時間分に限定するという独自の判断を示しました。
(4) 45時間という時間数の意義
判決が「45時間」という時間数を採用した根拠は、当時の労働省告示(36協定の限度時間)と厚生労働省通達(健康確保の観点)です。定額残業代制度の設計において「45時間」という時間数が重要な基準となることを示した点で、実務上大きな意義があります。
ただし、36協定の限度基準告示は労働契約に対する強行的補充的効力(労基法13条)を有するわけではなく、絶対的上限ではないという点で、理論的には疑問も残ります。
5.本判決からの実務上の留意点
(1) 定額残業代の対象時間数
本判決から得られる最も重要な実務上の教訓は、定額残業代の対象時間数は月45時間程度に設定するのが望ましいということです:
– 労働時間の限度基準(36協定の限度時間)に合わせて設計する
– 健康確保の観点からも月45時間程度を上限とする
– 45時間を大幅に超える設定は、安全配慮義務違反や公序良俗違反と判断されるリスクがある
– 長時間の時間外労働を「義務」として課すことを避ける
(2) 制度の設計と運用の一貫性
本判決では、賃金規程と実際の計算方法の不整合や、職務手当と別途支給される深夜手当の関係の不明確さが指摘されています:
– 賃金規程と実際の計算方法・運用を一致させる
– 定額残業代が対象とする割増賃金の種類を明確にする(時間外、休日、深夜など)
– 複数の手当が存在する場合は、その関係性を明確にする
– 規程間で齟齬が生じないよう整合的に設計する
(3) 労働時間管理と差額支払い
本件では差額支払実績がなかったことが「無限定な定額時間外賃金に関する合意」と認定された一因です:
– 実際の労働時間を適切に管理・把握する
– 定額残業代の対象時間を超える場合は必ず差額を支給する
– 差額支払いの実績を残す(給与明細への明確な記載など)
– 「いかなる場合も定額残業代以外は支払わない」という方針は持たない(強行法規違反)
(4) 労働時間の実態調査
定額残業代の対象時間数を合理的に設定するためには:
– 労働時間の実態調査を行い、平均的な時間外労働時間を把握する
– 調査結果に基づいて定額残業代の対象時間数を設定する
– 月45時間を大幅に超える場合は、業務量・人員配置の見直しを検討する
– 調査資料は保存し、合理的な制度設計の根拠として活用する
本判決の重要なメッセージは、定額残業代制度は単なる「支払方法」ではなく、労働者の「労働義務」にも関わる制度だということです。そのため、労働時間法制の趣旨(労働時間の上限規制、健康確保)に沿った制度設計が求められます。月45時間程度を目安とし、労働者の健康に配慮した適切な制度設計と運用が重要です。
Y工務店事件(東京地判平25.6.26)【組込型・無効】★★☆
1.本判決を紹介する意義
本判決は、一つの定額残業代が複数種類の割増賃金(時間外、休日、深夜)に対応するとされていた場合の問題点を指摘した重要事例です。定額残業代の「明確区分性」要件について、通常賃金と割増賃金の区分だけでなく、「複数種類の割増賃金間の内訳」まで明確にすべきという新たな判断基準を示しました。
この判決は、定額残業代制度の設計において従来あまり注目されていなかった「複数種類の割増賃金を対象とする場合の留意点」を明らかにした点で、実務上重要な意義を持っています。
2.事案
(1) 概要
被告Y社(Y工務店)の従業員(営業職)であった亡Aの相続人である原告Xら3名が、割増賃金および付加金の支払いを求めて提訴しました。
Y社は、基本給の40%はみなし残業代(定額残業代)であり、それは月85時間分の時間外労働に対する時間外手当として合意されていたと主張しました。
(2) 規程の定め等
労働条件通知書(雇用契約書):
賃金について「基本給月額21万円」(入社時から徐々に昇給し、最終的には23万1,750円となっていた)と「みなし残業代の割合40%」と記載されており、割増賃金率の項には「みなし労働者や年俸者の場合は金額の4割を相当分としています」と規定されていました。
なお、「みなし労働者」とは事業場外みなし労働時間制の適用を受ける者のことで、亡Aは「みなし労働者」とされていました。
給与規則:
「(23条3項)
営業SF職・AL職の基本給及び調整給の60%或いは65%を本給とし、40%ないし35%を超過勤務・深夜勤務・休日勤務手当とする。」
→40%ないし35%の間でどの割合にするかは個別契約で決定されており、亡Aについては労働条件通知書のとおり40%とされていました。
(3) 争点
Y社は、以下の計算式に基づき、基本給中のみなし残業代は1か月85時間分の時間外労働に対する割増賃金であると主張しました。
(Y社主張の計算式)
21万円×60%÷160.63時間(月平均所定労働時間)=784円(時間給)
784円×1.25=980円(割増時給)
21万円×40%÷980円=85時間
Y社の主張によれば、基本給の40%は全額が超過勤務手当、すなわち時間外労働85時間分の定額残業代ということになります。また、基本給が昇給するに伴い、定額残業代(時間外手当)の金額も上昇したと主張していました。
これに対し、Xらはこのみなし残業代(定額残業代)は無効であると主張しました。
3.判決の内容
「被告は、Aの給与の40%が85時間相当のみなし残業代であったと主張するが、①被告の主張する計算式には、休日、深夜、月60時間超の割増が考慮されていない。
②給与の40%に相当する時間外労働時間は、休日、深夜、月60時間超の時間がそれぞれ何時間あったかで変動するものであって、上記の規定だけからは、給与の40%に相当する時間外労働時間を確定することができない。
③したがって割増賃金に当たる部分がそれ以外の賃金部分と明確に区別されているとはいえない。
④また、仮にAが給与の40%がみなし残業代であることに納得していたとしても、無効な給与規則に基づくものである以上、その合意も無効である。」
4.検討
(1) 給与規則とY社主張の齟齬
Y社の給与規則23条3項では、基本給のうち40%が「超過勤務・深夜勤務・休日勤務手当」に相当すると定められていました。つまり、定額残業代はこれら3種類の割増賃金に対応するという建て付けでした。
一方、Y社の訴訟上の主張によると、基本給の40%は時間外労働85時間分の時間外手当のみに相当するとしていました。これは、給与規則の定めと明らかに矛盾しています。
本判決はこの齟齬を指摘した上で、複数種類の割増賃金を対象とする定額残業代の問題点を詳細に検討しています。
(2) 複数種類の割増賃金と明確区分性
本判決の重要な指摘は、定額残業代が複数種類の割増賃金を対象とする場合、各種割増賃金の内訳(金額・時間数)が明確でなければ「明確区分性」要件を満たせないという点です。
判決は、「給与の40%に相当する時間外労働時間は、休日、深夜、月60時間超の時間がそれぞれ何時間あったかで変動する」と述べています。つまり、割増率の異なる労働(時間外、休日、深夜、月60時間超)の各時間数が明確でないと、定額残業代が何時間分に相当するのか確定できないという問題を指摘しています。
これは、定額残業代の「明確区分性」要件を厳格に解釈した判断であり、従来は通常賃金部分と割増賃金部分の区分だけが問題とされていましたが、複数種類の割増賃金間の内訳まで明確にすべきという新たな基準を示したものといえます。
(3) 「給与規則無効」の判断について
判決は「無効な給与規則に基づくものである以上、その合意も無効である」と述べていますが、なぜ給与規則が無効なのかについての明確な理由付けはありません。
理論的には、給与規則の定めが不明確であることは、定額残業代の「明確区分性」という要件を満たさないという問題であり、規則自体が無効になるというよりは、当該規定から定額残業代の合意内容が認定できないという解釈上の問題と考えられます。
給与規則自体が無効になるというのは論理の飛躍があり、本判決はこの点で合意内容の認定・解釈の問題と合意の有効性の問題を混同している可能性があります。
5.本判決からの実務上の留意点
(1) 単一種類の割増賃金に絞った定額残業代設計
本判決から得られる最も重要な実務上の教訓は、定額残業代は一種類の割増賃金のみを対象とするシンプルな制度設計が望ましいということです:
– 時間外、休日、深夜など複数の割増賃金を一つの定額残業代で対応させない
– 時間外労働のみを対象とした定額残業代、休日労働のみを対象とした定額残業代というように種類別に分けて設計する
– 各定額残業代の対象とする割増賃金の種類を就業規則や労働契約書に明記する
– 各定額残業代について対象時間数と金額を明確に設定する
(2) 複数種類を対象とする場合の内訳明示
どうしても一つの定額残業代で複数種類の割増賃金を対象とする場合は:
– 各種割増賃金の内訳(時間数と金額)を明確に規定する
– 例えば「時間外労働30時間分(○○円)、休日労働8時間分(○○円)、深夜労働10時間分(○○円)」というように内訳を明示する
– 就業規則や労働契約書だけでなく給与明細書にも内訳を記載する
– 実際の割増賃金計算と定額残業代との差額を計算する際の充当順序も明確に規定する(例:時間外→休日→深夜の順に充当するなど)
(3) 給与規則と運用の整合性確保
本件では給与規則と実際の運用(Y社の主張)に齟齬があり、これが問題視されました:
– 給与規則と実際の運用を一致させる
– 給与規則改定の際は、定額残業代の対象となる割増賃金の種類や計算方法も含めて整合的に修正する
– 運用を変更する場合は給与規則も合わせて改定する
– 従業員への説明内容と規則の内容を一致させる
(4) 対象時間数の適正化
本件では定額残業代が月85時間分という長大な時間数を対象としていました:
– 月45時間程度を目安とした適正な時間数設定を行う
– 労働時間の実態調査に基づいて合理的な時間数を設定する
– 極端に長時間の定額残業代設定は「残業代支払いを免れるための便法」と見なされるリスクがある
– 月60時間超の時間外労働については割増率が50%以上となることにも留意する
本判決は、定額残業代制度の設計において従来あまり注目されていなかった「複数種類の割増賃金を対象とする場合の問題点」を明らかにした重要な判例です。複数種類の割増賃金を一つの定額残業代で対応させることは、制度の複雑化やリスク増大につながるため、できるだけ避けるべきという教訓が得られます。
ファニメディック事件(東京地判平25.7.23)【組込型・無効】★★★
1.本判決を紹介する意義
本判決は、櫻井補足意見とは異なるアプローチで定額残業代の明確区分性を判断した重要事例です。アクティリンク第二事件と同じ裁判官が担当しながらも、「明確区分性の趣旨」について独自の解釈を示した点が注目に値します。
特に、明確区分性が求められる趣旨を「労働者による確認可能性」に求めた点と、定額残業代制度の合理性を実質的に判断した点で実務に大きな影響を与える判例です。また、定額残業代の対象時間数に関して「月45時間」という目安を示した点も実務上重要な意義を持ちます。
2.事案
(1) 概要
被告Y社(ファニメディック)は、動物の診療施設の経営などを行う会社です。原告Xは獣医師としてY社に入社しましたが、試用期間満了時にY社から雇用契約を終了する意思表示を受けました。これに対しXは、地位確認や未払割増賃金の支払いを求めて提訴しました。
Xの基本給は月額30万2,000円で、判決では月所定労働時間は173.8時間として計算されています。
(2) 定額残業代に関する規程の定め
Y社の賃金規程11条には以下のような定めがありました:
「第11条(基本給の決定)
基本給は、従業員の能力、経験、技能、職務内容及び勤務成績などを総合的に勘案して各人ごとに決定する。
2 獣医師の基本給は、各人別に算定される能力基本給および年功給により構成されるものとし、以下の式により算出される金額を75時間分の時間外労働手当相当額及び30時間分の深夜労働手当相当額として含むものとする。
75時間分の時間外労働手当相当額=(能力基本給+年功給)×34.5%
30時間分の深夜労働手当相当額=(能力基本給+年功給)×3.0%
5 その月の時間外労働手当、法定休日労働手当及び深夜労働手当の合計額が前各号の時間外労働手当相当額を超える場合には、会社は、その超過分について支払う。」
(3) 争点と主張
賃金規程に基づき、基本給に割増賃金が含まれて支給されていたといえるか否かが争われました。
Xは、「Xが勤務していた事業所では、一か所を除いて36協定が締結されていなかったのであるから、Y社が時間外労働を命じること自体違法であり、定額残業代の定めも無効である」と主張しました。また、「賃金規程の定めでは通常の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分が判別できない。さらに、基本給中の時間外手当相当額を引き上げる際、支給額を増額するのでなく時間外手当の割合を操作するというY社の規定は、労基法の潜脱である」とも主張しました。
3.判決の内容
(1) 36協定との関係についての判断
「有効な36協定が締結されていない状況下でなされた時間外労働にも割増賃金は発生すること、その際、就業規則に労基法に定めるものと同等か、それ以上の割増賃金に関する定めがあれば、使用者に対し、当該規定に基づく支払義務を課すことが相当であることに照らせば、36協定の効力の有無によって、割増賃金に関する就業規則の規定の効力は影響を受けないというべきである。」
(2) 定額残業代規定の合理性
「本件固定残業代規定の合理性の有無が問題となるが、割増賃金を労基法37条に定める計算方法によらずに支払うことも、どの部分が割増賃金に相当するかが明確であり、かつそれが労基法37条の計算による割増賃金を下回らない限り適法であるというべきであるから、そのような規定自体が不合理であるとまではいえない。」
(3) 明確区分性の趣旨と本件での判断
「基本給に時間外労働手当が含まれると認められるためには、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分が判別出来ることが必要であるところ(最高裁平成6年6月13日第二小法廷判決、裁判集民事172号673頁参照)、その趣旨は、時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分が労基法所定の方法で計算した額を上回っているか否かについて、労働者が確認できるようにすることにあると解される。」
「確かに、本件固定残業代規定に従って計算することで、通常賃金部分と割増賃金部分の区別自体は可能である。しかし、同規定を前提としても、75時間分という時間外労働手当相当額が2割5分増の通常時間外の割増賃金のみを対象とするのか、3割5分増の休日時間外の割増賃金をも含むのかは判然とせず、契約書や給与支給明細書にも内訳は全く記載されていない。
結局、本件固定残業代規定は、割増賃金部分の判別が必要とされる趣旨を満たしているとはいい難く、この点に関するY社の主張は採用できない(そもそも、本件固定残業代規定の予定する残業時間が労基法36条の上限として周知されている月45時間を大幅に超えていること、4月改定において同規定が予定する残業時間を引き上げるにあたり、支給額を増額するのではなく、全体に対する割合の引上げで対応していること等にかんがみれば、本件固定残業代規定は、割増賃金の算定基礎額を最低賃金に可能な限り近づけて賃金支払額を抑制する意図に出たものであることが強く推認され、規定自体の合理性にも疑問なしとしない。)」
(4) 結論と付加金
本判決は、「基本給全体が割増賃金の基礎となる賃金に当たるというべきである」として、未払割増賃金の請求についてほぼ請求額全額(48万2,445円)を認容しました。さらに、付加金として認容額とほぼ同額(47万円)の支払いも命じました。
4.検討
(1) 明確区分性の趣旨に関する解釈
本判決の最大の特徴は、明確区分性が求められる趣旨について独自の解釈を示した点です。判決は、明確区分性の趣旨を「時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分が労基法所定の方法で計算した額を上回っているか否かについて、労働者が確認できるようにすること」と明確に述べています。
これは、櫻井補足意見が示した「罰則適用の有無を判断できるようにするため」という趣旨とは明らかに異なる解釈です。本判決は、明確区分性の趣旨を「労働者保護」の観点から捉えているといえます。
この趣旨からすれば、定額残業代部分の判別は、少なくとも金額によってなされていれば足りるはずですが、本判決は複数種類の割増賃金に対応する場合の内訳の明確性も求めています。
(2) 複数種類の割増賃金と明確区分性
本判決は、Y社の定額残業代規定について、「75時間分という時間外労働手当相当額が通常時間外の割増賃金のみを対象とするのか、休日時間外の割増賃金をも含むのかは判然としない」と指摘しています。
これは、先のY工務店事件と同様に、複数種類の割増賃金を一つの定額残業代で対応させる場合の問題点を指摘したものといえます。割増率の異なる労働(時間外、休日等)の内訳が不明確な場合、労働者が「定額残業代が法定の割増賃金を上回っているか」を確認できないため、明確区分性の趣旨を満たさないという判断です。
(3) 定額残業代制度の実質的合理性判断
本判決の特筆すべき点として、定額残業代制度の実質的合理性を詳細に検討していることが挙げられます。判決の括弧書き部分では、次の点を指摘しています:
1. 定額残業代の対象時間が「月45時間」という上限を大幅に超えていること(本件では75時間)
2. 時間外労働時間の引上げ時に、支給額増額ではなく割合の引上げで対応していること
3. これらから「割増賃金の算定基礎額を最低賃金に可能な限り近づけて賃金支払額を抑制する意図」が推認されること
特に、定額残業代の対象時間数について「労基法36条の上限として周知されている月45時間」を基準としている点は重要です。月45時間という時間数が定額残業代制度の設計において一つの目安となることを示唆しています。
(4) 36協定と定額残業代制度の関係
本判決は、36協定の有無が定額残業代制度の有効性に直接影響しないという重要な判断も示しています。これは実務上も有意義な判断であり、36協定未締結の事業場でも定額残業代自体は無効にならないという点を明確にしています。
ただし、合理性判断の中で「36条の上限として周知されている月45時間」に言及しており、間接的には36協定の基準が定額残業代制度の合理性判断に影響することも示しています。
5.本判決からの実務上の留意点
(1) 複数種類の割増賃金の内訳明示
本判決から得られる最も重要な教訓は、複数種類の割増賃金を対象とする定額残業代では、各種類の内訳を明確にすべきということです:
– 時間外、休日、深夜など種類ごとの内訳(時間数と金額)を明示する
– 就業規則や労働契約書に各割増賃金の種類と内訳を記載する
– 給与明細書にも内訳を明記する
– 可能であれば、一つの定額残業代で複数種類の割増賃金を対象としないシンプルな設計を採用する
(2) 定額残業代の対象時間数
本判決は「月45時間」を一つの目安として示しています:
– 定額残業代の対象時間数は月45時間程度を目安とする
– 45時間を大幅に超える設定は合理性を疑われるリスクがある
– 長時間の定額残業代設定は「賃金支払額を抑制する意図」と評価される可能性がある
– 労働時間の実態調査に基づいた合理的な時間数設定を行う
(3) 割増賃金の割合操作に注意
本判決は、「時間外労働時間の引上げ時に、支給額増額ではなく割合の引上げで対応」していたことを問題視しています:
– 時間外労働時間を引き上げる場合は、それに見合った支給額の増額を行う
– 基本給総額を維持したまま定額残業代の割合だけを増やす方法は避ける
– 割合操作によって通常賃金部分を減らし、算定基礎額を抑制する方法は不合理と判断されるリスクがある
– 定額残業代制度の変更時には、労働者の不利益にならないよう配慮する
(4) 規程間の整合性確保
本件では、賃金規程内で食い違いがあるように見える部分があり、それが問題視されています:
– 賃金規程内の各条項間での整合性を確保する
– 規程と実際の運用を一致させる
– 賃金規程と労働契約書・給与明細書の記載を整合的にする
– 規程変更時には全体の整合性をチェックする
(5) 労働者による確認可能性の確保
本判決は明確区分性の趣旨を「労働者が確認できるようにすること」と明確に述べています:
– 定額残業代の計算方法を労働者に明確に説明する
– 採用時や制度変更時に書面で詳細を通知する
– 給与明細書に定額残業代の対象時間数、金額、内訳を明記する
– 差額発生時の計算方法も明確に説明する
本判決は、定額残業代制度が形式的要件を満たすだけでなく、実質的にも合理的であることが求められることを示しています。「賃金支払額を抑制する意図」と評価されないよう、実態に即した適正な制度設計と運用が重要です。
第5章:テックジャパン事件からの軌道修正
日本ケミカル事件(最一小判平30.7.19)【手当型・有効】★★★
1.本判決を紹介する意義
本判決は、固定残業代制度の有効性判断について最高裁が新たな判断枠組みを明確に示した極めて重要な判例です。
特に、テックジャパン事件最高裁判決の櫻井補足意見以降に広がった厳格な要件論に対して、最高裁として明確な軌道修正を行った画期的な判決といえます。
本判決の最大の意義は、「定額残業代の有効性は契約の内容によって定まり、その他に何らかの独立の要件を必要とするものではない」という根本的な考え方を最高裁が明確に示した点にあります。
これにより、テックジャパン事件以降の下級審で見られた過度に厳格な要件設定に歯止めがかかり、実務上も大きな影響を与えています。
2.事案
(1) 概要
被上告人X(元従業員)は、保険調剤薬局の運営を主たる業務とする上告人Y社(日本ケミカル)に薬剤師として雇用されていました。平成24年11月10日に締結された雇用契約では、基本給46万1,500円、業務手当10万1,000円の賃金構成となっていました。
Xは平成25年1月21日から平成26年3月31日までの間、Y社が運営する薬局において薬剤師として勤務し、上記の基本給及び業務手当の支払いを受けました。その後、Xは時間外労働等に対する賃金並びに付加金等の支払いを求めて提訴しました。
(2) 労働時間等の実態
Xの1か月当たりの平均所定労働時間は157.3時間でした。実際の時間外労働等の状況を賃金計算期間(1か月間)ごとに見ると、全15回のうち:
- 30時間以上:3回
- 20時間未満:2回
- 20時間台:10回
という状況でした。
(3) 固定残業代に関する規程・契約内容
本件雇用契約書:
- 「月額562,500円(残業手当含む)」
- 「給与明細書表示(月額給与461,500円 業務手当101,000円)」
採用条件確認書:
- 「月額給与 461,500」
- 「業務手当 101,000 みなし時間外手当」
- 「時間外勤務手当の取扱い 年収に見込み残業代を含む」
- 「時間外手当は,みなし残業時間を超えた場合はこの限りではない」
Y社の賃金規程:
「業務手当は,一賃金支払い期において時間外労働があったものとみなして,時間手当の代わりとして支給する。」
他の従業員との確認書:
「業務手当は,固定時間外労働賃金(時間外労働30時間分)として毎月支給します。一賃金計算期間における時間外労働がその時間に満たない場合であっても全額支給します。」
(4) 労働時間管理の実態
Y社はタイムカードを用いて従業員の労働時間を管理していましたが、タイムカードに打刻されるのは出勤時刻と退勤時刻のみでした。
Xは平成25年2月3日以降、休憩時間に30分間業務に従事していましたが、これについてはタイムカードによる管理がされていませんでした。
また、Y社がXに交付した毎月の給与支給明細書には、時間外労働時間や時給単価を記載する欄がありましたが、これらの欄はほぼ全ての月において空欄でした。
3.下級審の判断
(1) 第一審(東京地裁立川支部判平28.3.29)
第一審は、事実関係に照らして、Y社がXに対して給与のうち基本給が46万1,500円、みなし時間外手当として支給される業務手当が10万1,000円である旨を説明し、Xはこれを了解して本件雇用契約を締結したものと認定しました。
そして、業務手当がみなし時間外手当として有効かについて、以下の2点を指摘して有効と判断しました:
① Y社においては、業務手当を30時間分の時間外手当と認定していることが認められ、Y社代表者によりXに対し、みなし残業時間の設定時間についても、その旨一応の説明がされていると認められること
② みなし時間外手当に対応する時間外労働時間を超過する時間外労働については、実際にみなし時間外手当とは別に時間外手当が支払われるなど、業務手当を超える部分について、時間外手当の精算がされていること
結論として、主としてY社において休憩時間とされていた時間の一部を労働時間として算定し直した結果生じた未払残業代のみXの請求を認容し、その余の請求は棄却しました。
(2) 原審(東京高判平29.2.1)
原審は、Xの請求をより広く認める形で一審判決を変更しました。
原審は、定額残業代の有効性について極めて厳格な判断枠組みを示しました:
「いわゆる定額残業代の仕組みは、定額以上の残業代の不払の原因となり、長時間労働による労働者の健康状態の悪化の要因ともなるのであって、安易にこれを認めることは、労働関係法令の趣旨を損なうこととなり適切でない。
①定額残業代を上回る金額の時間外手当が法律上発生した場合にその発生の事実を労働者が認識して直ちに支払を請求できる仕組み(発生していない場合には発生していないことを労働者が認識できる仕組み)が備わっており、これらの仕組みが雇用主により誠実に実行されており、
②基本給と定額残業代の金額のバランスが適切であり、
③その他法定の時間外手当の不払や長時間労働による健康状態の悪化など労働者の福祉を損なう出来事の温床となる要因がない場合に限り、定額残業代の支払を法定の時間外手当の全部又は一部の支払とみなすことができると解される」
そして、この判断枠組みに基づき、本件では以下の理由から業務手当の支払を法定の時間外手当の支払とみなすことはできないと判断しました:
① 業務手当の性質(業務手当が何時間分の時間外手当に当たるのか)がXに伝えられていないこと
② 昼間の2時間半の休憩時間中の時間外労働の発生の有無を管理・調査する仕組みがないためXの時間外労働の合計時間を測定することができないこと
③ Xに時間外労働の月間合計時間や時給単価が誠実に伝えられていないため、定額の業務手当を上回る金額の時間外手当が発生しているかどうかをXが認識することができないこと
4.最高裁判決の内容
(1) 労働基準法37条の趣旨と定額残業代制度の位置づけ
最高裁は、まず労働基準法37条の趣旨を確認した上で、定額残業代制度の基本的な位置づけを明確にしました:
「労働基準法37条が時間外労働等について割増賃金を支払うべきことを使用者に義務付けているのは、使用者に割増賃金を支払わせることによって、時間外労働等を抑制し、もって労働時間に関する同法の規定を遵守させるとともに、労働者への補償を行おうとする趣旨によるものであると解される。
また、同条は、労働基準法37条等に定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまるものと解され、労働者に支払われる基本給や諸手当にあらかじめ含めることにより割増賃金を支払うという方法自体が直ちに同条に反するものではなく、使用者は、労働者に対し、雇用契約に基づき、時間外労働等に対する対価として定額の手当を支払うことにより、同条の割増賃金の全部又は一部を支払うことができる。」
(2) 定額残業代の有効性判断の基本的枠組み
最高裁は、定額残業代の有効性判断について、以下の基本的な考え方を示しました:
「雇用契約においてある手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされているか否かは、雇用契約に係る契約書等の記載内容のほか、具体的事案に応じ、使用者の労働者に対する当該手当や割増賃金に関する説明の内容、労働者の実際の労働時間等の勤務状況などの事情を考慮して判断すべきである。
しかし、労働基準法37条や他の労働関係法令が、当該手当の支払によって割増賃金の全部又は一部を支払ったものといえるために、前記3(1)のとおり原審が判示するような事情が認められることを必須のものとしているとは解されない。」
この判示において最高裁は、原審が示した厳格な要件を明確に否定しています。
(3) 本件への具体的当てはめ
最高裁は、本件の事実関係に基づいて以下のように判断しました:
契約上の位置づけについて:
「本件雇用契約に係る契約書及び採用条件確認書並びに上告人の賃金規程において、月々支払われる所定賃金のうち業務手当が時間外労働に対する対価として支払われる旨が記載されていたというのである。また、上告人と被上告人以外の各従業員との間で作成された確認書にも、業務手当が時間外労働に対する対価として支払われる旨が記載されていたというのであるから、上告人の賃金体系においては,業務手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものと位置付けられていたということができる。」
実態との整合性について:
「被上告人に支払われた業務手当は、1か月当たりの平均所定労働時間(157.3時間)を基に算定すると、約28時間分の時間外労働に対する割増賃金に相当するものであり、被上告人の実際の時間外労働等の状況と大きくかい離するものではない。」
結論:
「これらによれば、被上告人に支払われた業務手当は、本件雇用契約において、時間外労働等に対する対価として支払われるものとされていたと認められるから、上記業務手当の支払をもって、被上告人の時間外労働等に対する賃金の支払とみることができる。原審が摘示する上告人による労働時間の管理状況等の事情は、以上の判断を妨げるものではない。」
5.本判決の検討
(1) 判例としての位置づけと画期的意義
本判決の最大の意義は、テックジャパン事件最高裁判決の櫻井補足意見以降に下級審で広がった厳格な要件論に対して、最高裁として明確な軌道修正を行った点にあります。
具体的には、以下の点で画期的な転換を示しています:
① 「対価性」の判断枠組みの確立
「時間外労働等に対する対価として支払われるものとされているか否か」という「対価性」を中心とした判断枠組みを明確に示しました。
② 契約内容による判断の重視
定額残業代の有効性は「契約の内容によって定まり、その他に何らかの独立の要件を必要とするものではない」という根本原則を明確にしました。これは、櫻井補足意見が示した差額支払合意や時間数・金額の明示等の要件を明確に否定するものです。
③ 総合的・実質的判断の採用
契約書等の記載内容だけでなく、使用者の説明内容、実際の勤務状況等を総合的に考慮して判断するという柔軟なアプローチを示しました。
(2) 対価性の判断要素
本判決は、定額残業代の「対価性」を以下の2つの要素で判断しています:
① 契約上の位置づけ
- 契約書等における記載内容
- 使用者の労働者に対する説明内容
- 賃金規程等における位置づけ
② 実態との整合性
- 定額残業代の金額と実際の時間外労働等の状況との整合性
- 大きなかい離がないこと
この2要素が満たされれば、定額残業代として有効と認められるという明確な判断基準を示しています。
これは、最高裁として、固定残業代の割増賃金該当性について、
- 契約書の記載や使用者の説明等に基づく労働契約上の対価としての位置づけ、および
- 実際に勤務状況に照らした手当と実態との関連性・近接性
を要件とする判断枠組みを提示したようにも読めます。
このような判断枠組みによれば、契約書への記載や使用者の説明が不十分な場合は①契約上の位置づけ要件を欠き、契約書への記載が十分あっても,手当の性質や金額が時間外労働等の実態と関連・近接していない場合には②実態要件を欠くとして、固定残業代の支払が割増賃金の支払いと認められないと解されるとも思われます。
ただ,筆者としては,②の実態まで要件であると解するのは論理的ではなく不当であると考えます。
なぜならば,雇用契約書や賃金規程において,ある手当が(仮に発生した場合の)時間外労働の対価として支払うことを明示され労働契約の内容となっている以上,仮に実態との乖離があったとしても,それは労働契約の内容に影響を及ぼさないはずだからです。
例えば,45時間分の時間外労働相当の固定残業代を雇用契約で明確に定めた場合,契約後,使用者の残業抑止策によって実際には残業が20時間程度に留まったとした場合,本件最高裁の判断枠組みによれば「実態との乖離がある」として,事後的に無効とされることにもなりかねません。
契約後の事情によって契約時の合意内容を判断することは,論理的ではないのみならず,契約の予測可能性を奪い妥当ではないのです。
なお、その後の裁判官による評釈論文や協議会において、上記②の支払額と実際の勤務状況との乖離していない,という点は,必須の要件ではないことを明らかにされています。
「雇用契約に基づいて支払われる手当契約の内容がどのようなものであるかが,時間外労働等に対する対価として支払われるものとされているか否かは,契約の内容によって定まり,その他に何らかの独立の要件を必要とするものではないことを明らかにするとともに,は,契約書等の記載内容のほか, 具体的事案に応じ,使用者の労働者に対する当該手当や割増賃金に関する説明の内容,労働者の実際の労働時間等の勤務状況などの事情を考慮して総合的に判断すべきことを明らかにしたものといえる。一般に,契約の内容の認定を行うにあたり,契約書等の記載内容に加え,締結時やその前後の当事者の言動等を総合的に考慮することは通常行われていると思われる。雇用契約についても基本的に異なるところはなく,契約書等の記載内容が大きな手がかりとなるものの,契約書等の記載内容からは当該手当の趣旨が一義的に明確でない場合であっても,毎月の支給時には当該手当が何時間分の残業代に相当するものであるかなどの事項を説明している場合には時間外労働等に対する対価として支払われるものと認められる場合もあり得るところであるし,そのほかにも, 当該手当を受領している労働者の勤務状況や業務内容等から, 当該手当は時間外労働等に対する対価として支払われるものと推認されるか,逆に勤務状況等から別の趣旨で支払われるものと推認されるかなどの事情を考慮して判断することになることを示したものと思われる。上記の判示は,このような趣旨であるから,契約書等の記載内容,説明内容,実際の勤務状況等がそれぞれ必須の要件や要素となることを示したものとは解されないであろう。」(ジュリスト2532号P79,最高裁調査官池原桃子)。
「固定残業代という記載が雇用契約書等に明示されているという場合でありましても,対価性の検討に当たって,固定残業代の額に相当する労働時間と実際の労働時間との乖離のみが重要な事情となる事は考えがたいと思われます。」「日本ケミカル事件において示された考慮要件は,契約内容を認定するに当たって用いられる一般的な判断手法を,同事件の事案に即した形で表現し直したものと考えられます。労働事件でも,一般的にその契約の解釈が問題になるような場合については,同様の判断手法で双方当事者から主張,立証を頂いているかと思いますので,そこは固定残業代の場合でも基本的に変わらないかと考えております。」(労働判例1217号P24~25 東京地裁労働部と東京三弁護士会の協議会)。
(3) 櫻井補足意見との関係
本判決は、テックジャパン事件の櫻井補足意見が示した以下の要件を明確に否定しています:
- 支給時における時間外労働の時間数と残業手当額の明示
- 差額支払合意の事前明示
- 労働者の認識可能性確保の仕組み
この点について、水町勇一郎教授は「客観的な実態に基づいて判断されるべき強行法規である労基法37条の解釈として、労働者の主観的認識や抽象性の高い要件を取り込んでいた本件原審判決(その前提にあった櫻井補足意見)を軌道修正した」と評価しています(水町勇一郎「詳解労働法[3版]」P738頁(2023年9月)。
(4) 労働時間管理状況の位置づけ
本判決で注目すべきは、原審が問題視した労働時間管理の不備(休憩時間中の労働時間の管理不備、給与明細書の記載不備等)について、「以上の判断を妨げるものではない」と明確に述べている点です。
これは、労働時間管理の不備が定額残業代の有効性を直ちに否定する要因ではないことを示しており、実務上重要な判断です。
ただし、労働時間管理の不備により実際に未払い残業代が発生している場合は、当然にその差額の支払義務は生じます。
(5) 金額の妥当性について
本件では、業務手当10万1,000円が約28時間分の時間外労働に対する割増賃金に相当し、実際の時間外労働の状況(20時間台が多く、30時間以上は3回のみ)と「大きくかい離するものではない」と判断されました。
この判断は、定額残業代の金額設定において完全に実態と一致する必要はなく、「大きくかい離しない」程度の整合性があれば足りることを示しています。
6.本判決を踏まえた実務対応
(1) 基本的な制度設計
本判決を踏まえると、定額残業代制度の設計において重要なのは以下の2点です:
① 契約上の明確化
- 雇用契約書や労働条件通知書に定額残業代の趣旨を明記する
- 賃金規程等でも定額残業代の位置づけを明確にする
- 採用時に定額残業代の趣旨を説明し、労働者の理解を得る
② 実態との整合性確保
- 事前に労働時間の実態調査を行う
- 調査結果に基づいて合理的な時間数・金額を設定する
- 定期的に実態と設定内容の整合性を確認する
- あまりにかけ離れた実態となっている場合は固定残業代の金額等の修正を検討する
(2) 従来の厳格要件への対応
本判決により、テックジャパン事件以降に要求されていた以下の要件は必須ではないことが明確になりました:
- 時間数・金額の労働者への事前明示
- 差額支払合意の明文化
- 労働者の認識可能性確保の具体的仕組み
ただし、実務上のリスク管理としては、これらの対応を行うことが依然として望ましいといえます。
(3) 労働時間管理との関係
本判決は労働時間管理の不備が定額残業代の有効性を直ちに否定するものではないことを示しましたが、以下の点に注意が必要です:
- 労働時間管理は労働基準法上の義務であり、適切な管理体制を構築する必要がある
- 長時間労働の防止や健康管理の観点からも適切な労働時間管理は重要
(4) 今後の裁判例への影響
本判決以降の下級審裁判例では、本判決の判断枠組みに沿った判断が増加しています。特に以下の傾向が見られます:
- 契約上の明確化と実態との整合性を重視する判断
- 過度に厳格な要件を設定しない傾向
- 労働時間管理の不備のみを理由とした定額残業代の無効判断の減少
7.本判決の意義と今後の展望
日本ケミカル事件最高裁判決は、固定残業代制度をめぐる議論に大きな転換点をもたらしました。
テックジャパン事件以降の過度な厳格化に歯止めをかけ、より実務的で合理的な判断枠組みを示したことで、企業にとっても労働者にとっても予見可能性の高い基準が確立されました。
本判決が示した「契約の内容による判断」「総合的・実質的判断」という考え方は、今後の固定残業代制度の設計・運用において基本となる重要な指針といえます。
ただし、本判決は定額残業代制度を無制限に認めるものではありません。適切な制度設計と運用、労働者の健康配慮、労働時間管理の徹底など、労働基準法の趣旨に沿った適正な制度運用が引き続き求められることに変わりはありません。
実務上は、本判決が示した判断枠組みを踏まえつつ、労働者の権利保護と企業の予見可能性確保の両立を図る制度設計と運用が重要となります。
荒木運輸事件(大阪地判令和4.11.24)【手当型・無効】★★☆
1.本判決を紹介する意義
本判決は、固定残業代制度が形式上の整備を満たしていたとしても、「対価性要件」および「判別要件」を欠く場合には無効と判断されることを明示した重要な裁判例です。
特に、本件手当が運送実績や等級評価に基づいて算出される成果給的な性質を持ち、労働時間との関係が薄いこと、また実際の残業時間と著しく乖離した金額であったことから、「実質的に通常労働の対価が混在している」と判断され、無効とされました。
形式的な規程整備だけでなく、算出根拠の合理性や残業代の実効的な支払が重要であることを再確認させる判決です。
2.事案
(1) 概要
被告・荒木運輸株式会社(貨物自動車運送事業)は、原告をトラック運転手として雇用し、雇用契約書には「業績給には一定の時間外手当を含む」との記載がありました。後に、業績給は「時間外割増」という名称に変更されました。
原告は、時間外・休日・深夜労働に対する未払割増賃金と付加金の支払いを求めて訴訟を提起しました。
(2) 給与規程の定め
荒木運輸の給与規程には以下のような記載がありました:
第3条 賃金体系:
基準内賃金(割増賃金の基礎に含まれる):
・基本給(等級に応じて設定)
・手当(役職手当・資格手当・無事故評価手当)
基準外賃金(割増賃金の基礎に含まれない):
・時間外割増(法所定の時間外手当)
・通勤費
・その他手当(詳細不明)第10条(時間外割増):
「日給者については、時間外割増とは法所定の時間外手当として支給する。第11条の計算額が時間外割増を上回るときは、その差額を別途支給する」
※平成30年3月の改定前、時間外割増は「業績給」とされ、売上評価(例:売上合計×0.8×25%)と等級評価(等級別評価額×出勤日数)を合算して算出されていました。
(3) 争点
被告は、本件「時間外割増」は固定残業代として有効であり、差額支給も行っていたため未払賃金は存在しないと主張。
一方で原告は、「時間外割増」は運行実績や等級評価を基にした成果給であり、時間外労働とは無関係な歩合給であるため、割増賃金の支払義務を果たしていないと反論しました。
主要な争点は、「時間外割増」が固定残業代として有効か否か、すなわち対価性要件・判別要件を満たすかでした。
3.判決の内容
(1) 手当の対価性の否定
雇用契約書には「時間外手当を含む」との文言がありましたが、算出根拠は労働時間とは無関係。
売上や等級評価は所定労働時間中にも発生するため、時間外労働との関係が不明確でした。
(2) 労働時間と手当額の乖離
固定残業代の対象時間として約200時間分が含まれていたのに対し、実際の時間外労働は月47時間程度。
この大きな乖離から、手当額が合理的水準を超えており、固定残業代制度としての妥当性を欠くと判断されました。
(3) 最低賃金割れの回避
基本給が最低賃金ギリギリの水準で、本件手当を含めないと最低賃金法に違反する月もありました。
この点からも、本件手当は通常労働時間の賃金としての性質を有すると評価されました。
(4) 求人票との乖離
求人票には基本給24.8万円〜36万円と記載されていたが、これは実際には手当を含む総額。
手当の性質について明確な説明もなく、労働者が「通常の賃金」と誤認する可能性が高いとされました。
以上を踏まえ、本件手当は「対価性要件」「判別要件」のいずれも満たさないとして、固定残業代としての有効性が否定されました。
4.検討
(1) 規程整備だけでは不十分
本件では、就業規則に「時間外割増」と明記されていたにも関わらず、実際の算出根拠・金額水準・労働実態の面から制度の実質が否定されました。
(2) 成果報酬型と固定残業代の混同に注意
売上や等級に基づいて変動する手当は、時間外手当ではなく成果給として評価されやすいため、制度設計時の明確な区分が必要です。
(3) 最低賃金との関係
最低賃金違反を回避するために成果給を通常賃金に組み込むような設計は、固定残業代の有効性を否定される要因となります。
5.実務上の留意点
- ? 固定残業代の算定根拠と金額の妥当性を明確にする
- ? 売上・等級など成果給要素と時間外手当を混同しない制度設計とする
- ? 固定残業代を除いた基本給で最低賃金をクリアする水準に設定
- ? 求人票・雇用契約書・説明資料間の整合性を確保する
- ? 実際の残業時間と支払手当額の差異を定期的に検証する
本判決は、制度の「形式」ではなく「実質」が厳しく問われる時代における、制度設計・運用上の重要な示唆を与える判例です。